




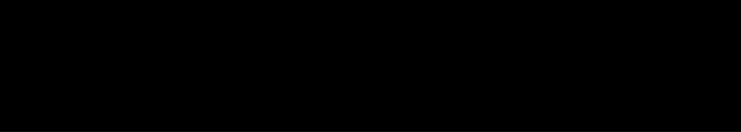



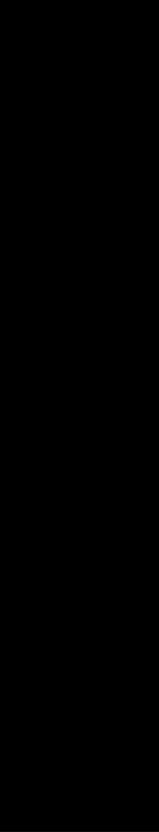
福田義昭
エジプト出張報告(2008年2月15日―3月2日)
2008年2月15日から同3月2日まで、エジプトのカイロに出張した。目的は(1)第4回カイロ「アラブ小説フォーラム」(2月17日-20日)への参加、(2)アラブ小説等に関する調査・資料収集の二つである。旅費に関しては、エジプトの最高文化評議会(المجلس الأعلى للثقافة)に日埃間の往復路運賃と2月20日までの滞在費を、NIHUプログラム「イスラーム地域研究」にそれ以降の滞在費等を負担していただいた。経費の出所からすると、本来ここでは、後半の調査についてのみ報告すべきかもしれない。しかし、互いに関連したものであり、あるいはまた関心を抱かれる方もいないとは限らないので、アラブ小説フォーラムについても簡単に報告しておきたい。(そもそも、今回のフォーラムに招いていただけたのも、最高文化評議会で仕事をしている筆者の友人らに加えて、昨年「イスラーム地域研究」の招聘により来日され、偶然面識を得たイマード・アブー・ガーズィー氏〔最高文化評議会諸委員会統括本部長〕に後押ししていただいた結果だと聞いた。)
(1)最高文化評議会が主催する「アラブ小説フォーラム」(ملتقى القاهرة للإبداع الروائي العربي)は、ちょうど10年前の1998年2月に始まった国際フォーラムで、今回は第4回目にあたる。毎回大きなテーマが設定され、参加者は原則として、そのテーマに沿った発表を行う。第1回目は「アラブ小説の特質」、第2回目(2003年)は「小説と都市」、第3回目(2005年)は「小説と歴史」がテーマであった。今回のテーマは「アラブ小説の現在」である。また、フォーラムの閉会式では、毎回アラブ人作家に対する授賞式が行われている。第1回目はサウジアラビア人(亡命)作家アブド・アル=ラフマーン・ムニーフ氏(1933-2004)、第2回目はエジプト人作家スヌアッラー・イブラーヒーム氏(1937-:ただし受賞拒否)、第3回目は(代表的作品『北へ遷りゆく時』の邦訳もある)スーダン人作家アル=タイイブ・サーリフ氏(1929-)、今回はアレクサンドリア出身のエジプト人作家エドワール・アル=ハッラート氏(1926-)が長年の功績により受賞した。
フォーラム会場では、二つの分科会で研究発表が行われるかたわら、並行して円卓討論会や他のセッションも開催された。初日を除き、朝の10時から昼休みを挟んで、夜の9時半ごろまでというハードなスケジュールにもかかわらず、連日連夜、たいへん活発な議論が倦むことなく繰り返されていた。研究者だけでなく、著名な作家や評論家も大勢、発表や討論会に参加した。参加者総数は210名を超えた。当然ながらエジプト人が断然多く、120名以上が参加していたが、他のアラブ諸国からも90名ほどが参加した。アラブ世界のほぼ全域から参加者があり、とりわけレバノン、シリア、イラク、モロッコからは、それぞれ10名を超える参加者があった。アラブ圏外からは、筆者を除いて5名が参加した。内訳は、ロシア、セルビア、イタリア、ギリシア、アメリカ合衆国各1名である。女性の参加者は全体の4分の1強を占めていた。会場では、開会の少し前に亡くなったエジプト人評論家のラガー・アル=ナッカーシュ(1934年生まれ)氏やフォーラム開催中に亡くなったフランス人作家アラン・ロブ=グリエ氏の死を悼んで、黙祷が捧げられた。
テーマが「アラブ小説の現在」だったため、アラブ世界において今、小説をめぐって、どのような問題が関心を呼んでいるのかを知る上で、フォーラムはたいへん有益なものだった。もちろん、すべての分科会やセッションに出席できたわけではないので、聞き逃した部分も多いのだが、関心の高さをうかがわせるトピックを、気づいた範囲で幾つか挙げてみよう。
まず女性をめぐる問題。一昔前のアラブ小説だと、有名な女性作家は数えるほどしかいなかった。しかし、昨今の女性作家の増加ぶりには目を見張るものがあり、質の高い作品も続々と生まれているようである。すでに、女性作家を対象にした研究書もかなり出ている。今回のフォーラムでも女性をテーマにした研究は多かった。また、「フェミニズム小説」や「女性作家による小説」、「女性をテーマ・主人公にした小説」などを意味する様々なアラビア語の批評用語をめぐっても批判的討論がなされていた。アラブの女性作家については「現代のシャハラザード」という、すでに少々手垢がついてしまった称号もよく用いられる。普通はシャハラザードの役割を高く評価してのことだろう。今回もその名を冠したセッションがあった。しかし一方で、シャハラザードは結局のところ男性が被った仮面のようなものでしかなく、真の女性の語り手ではないとして、シャハラザードは自分の「祖母」ではないと宣言する女性作家もいた。
自伝(的小説)に対する関心も高かった。近年、少なくともアラブ世界に関しては、自伝(的小説)に対する関心が高まっていると感じていたが、今回のフォーラムでも同様だった。特に最近の作品には、自伝的要素の濃厚なものが多いようである。この分野では、作家自身による発表(体験談)もあった。湾岸の某国の女性作家の場合、自伝的小説作品に盛り込まれた要素がもとで、自身はおろか、親族にまで迫害が加えられたという。フィクションと自伝の境界は常に問題になるが、理論上の議論はともかく、国家や社会が虚構作品と作者を区別してくれるとは限らない。現実に壇上で涙を流す彼女の姿を見て、作家自身がいかに勇気をもって日々闘いながら書いているか、改めて思い知らされた。
小説に描かれた都市や空間(場所)の問題、また歴史小説に対する関心も相変わらず高かった。先述のように、都市や歴史と小説の関わりについては、すでに過去のフォーラムで主要テーマになっている(それぞれの分厚い報告集[各3巻]も今フォーラム直前に出版され、入手することができた)。今回もまた同様のテーマを扱った発表が多かった。その背景には、実際、都市小説の比率が最近ますます上がっていることもあるだろうし、時空間ということに関しては近年のアラブ世界におけるミハイル・バフチンの人気もあると思われる。また歴史小説の分野では、古典作品の文体を取り入れたパロディ、パスティーシュ小説が数多く書かれていることもあるだろう。折しも、フォーラム会場の書店ブースで見つけて購入したスヌアッラー・イブラーヒームの最新作もそうした作品の一つだった。『ターバンと帽子』(2008)と題されたこの作品は、今まで現代物を書いてきた彼による初めての歴史物で、18世紀末のフランス軍によるエジプト(および東地中海)遠征とそれがエジプト社会に起こした波紋を、ジャバルティーの情報提供者でもある弟子の視点から語るという枠組みを採用している。ついでなので、この作品についても少し紹介しておくと、歴史的用語や俗語の使い方、正統的文章語からすると破格な要素など、文体はジャバルティーの年代記のそれをよく模倣しているような印象を(個人的には)受ける。さるインターネット・サイトに掲載されているインタビュー記事によると、どうやら、作者の狙いの少なくとも一つはイラクの現状を考えることにあるらしい。そうする上で、アラブ近代史上における外国支配の原体験とも言えるフランスのエジプト遠征を参照軸としてもってきたようである。もちろん、作中にイラクの話など出てこないが、ナポレオンのロジック(というかレトリック)を今読めば、米国大統領のそれを思い出さざるをえないし、エジプト社会に惹き起こされた混乱・暴動、外国人支配者への抵抗と協力、ムスリムとキリスト教徒の間の緊張関係等々、あちこちに両者間の並行的要素を見出すことになる。考えてみれば、シリアからやってきてクレーベル将軍を暗殺したムスリムなども、イラクにおける外国人のイスラーム主義者を思い出させないこともない。ちなみに、フィクション的要素ももちろんあるが、公的生活に関わる部分はほとんどすべて史実(あるいは歴史書等の記述)に基づいて書かれているようである。巻末には各種参考文献のほか、協力者としてラウーフ・アッバース氏やネリー・ハンナー氏ら著名な歴史家の名が挙げられている。
そのほか、ある円卓討論会では「デジタル小説」がテーマとなっていた。出席することはできなかったものの、いかにもアラブ小説の現在を表していておもしろい。アラブというより、世界的な同時現象なのだろうが、インターネットなど先端的コミュニケーション・ツールの普及は確かにアラブ小説にも新しい文体、テーマ、感性、需要と供給といったものを生み出しているらしい。筆者も、携帯電話による電子メール文体を取り入れた作品を見かけたことがある。また脱線するようだが、携帯電話と言えば、この種の会議ではいつも着信音が問題になる。今回のフォーラム会場でも実に多くの「着メロ」を聞くことになった。大抵は、セッションの司会者が前もって注意し、電源を切っておくようにと念を押すのだが、誰にもそれを守る気はなく、とりあえず電源は入れておくのだった。着メロだけならまだよいほうで、なかには発表中の会場で返事をしている人もいる。その度に誰かが注意する。しかし、また同じことが繰り返される。注意した本人の着メロが鳴ることもあった。果ては発表者の一人が壇上で(他の発表者がしゃべっているときではあるが)携帯電話の受け答えをしている光景も見られた。数年前のフォーラムでは、さる有名なアメリカ人研究者がこのような状況に激怒し、携帯電話を鳴らした聴衆との間で口論が起きたという話も聞いた。しかし、今回はそのような話も聞かなかった。こうした状況に批判的な人もいるにはいたが、諦めとともに受け入れているようであった。慣れれば、あまり気にならなくなるものである。そんななか、とある会議室にいると、セッションが始まる前に男性が入ってきて、聴衆に何やら小さな書物と思しきものを配り始めた。筆者も一冊もらったが、このプレゼントが『モバイル』と題された小説だったのには思わず笑ってしまった。
「若い作家たち」や「小説における映画的手法」に関するセッションなども組まれていた。また湾岸諸国での経験を描いたエジプト小説が幾つかの発表で取り上げられていた。これまでは、異文化体験となると──例外も皆無ではないものの──西洋諸国への旅を描くのが常道だった。最近では、湾岸諸国への旅を描く作品も増えてきたらしい。ほかに、「推理小説」に関する発表もあって、個人的には興味深かった。現代アラブ小説に関して以前から言われていることの一つに、SFとミステリーの欠如がある。SF的要素、ミステリー的要素を部分的に持った文学作品はあるが、本格的なSF作品やミステリー作品がほとんどない。外国作品の翻訳物がよく出ているのに対して、アラブ作家による優れた作品が出ないジャンルというのが、常識的な理解だろう。どうしてなのか昔から謎だった(宗教的な理由に帰してしまうのも、あまり説得力がないように思われる)。研究に関しても、今まで全くなかったわけではないが、そうした数少ない研究を読んでも、結局、アラブ小説における同ジャンルの貧困ぶりを印象づけられたような記憶がある。今回の発表でも、なぜこのジャンルが育たないかについて解答が得られたわけではない。しかし、この問題に対するまじめな関心自体は存在していること、また優れた作品を待望する空気があることは会場のやりとりから感じ取られた。
筆者を含めた外国人による発表についても一言述べておこう。率直に言えば、「アラブ小説の現在」というテーマは酷であった。筆者の友人いわく、このテーマは外国人研究者には「きつい」。最近は出版される小説作品の量も半端ではない。依然として、日本とは比較にならないほど詩の地位や人気が高いとはいえ、ある著名なエジプト人評論家は「小説の時代」を宣言している。昔と違ってマグリブ諸国や湾岸諸国からも数多くの作家が輩出している。我々にとっては、古典的といわれる作品を読むだけでも大変なので、新しい作品にはなかなか手が出ない。まだ英語やフランス語の話者であれば、数多くの作品を翻訳で手っ取り早く読むことができるが、日本語だとそれもかなわない。日本の研究者の層も薄い──というより、層と言えるほどのものはない──ので、何でも好きなことができる反面、めいめいが一から十までやらざるを得ず、特に現在のアラブ小説シーンを俯瞰するのは──自らの不勉強の言い訳にすぎないけれども──容易なことではない(とはいえ、欧米の研究者の多くも状況は似たり寄ったりの部分があり、一番多く読んでいるのは、むしろ翻訳を積極的に手がけている人たちかもしれない)。とにかくこのような事情から、外国人は少し論点をずらしたような発表が多かったようだ。筆者自身も、しかたなく「三つのエジプト小説」と題する発表を行った。五年ほど前から話題になって、社会現象とまで言われてきたアラー・アル=アスワーニーの小説『ヤコビヤン・ビル』(2002)を持ってきて、どうにか「現在」に引っ掛け、後は空間設定や語りの構造が同じ型に属する古い作品──ナギーブ・マフフーズの『ミダック小路』(1947)およびムスタファー・ムシャッラファの『背教者カンタラ』(1965)──と比較するというものであった。なお、今フォーラムで参加者に配布された『アラブ小説現況』は、斯界の最近の動向を各国の研究者が国別にまとめた予備的報告集であり、非常に便利なものである。
フォーラム終了後には、幾つかの問題点も指摘されていた。セッションによっては統一感がないと言われたり(これは筆者自身にも責任がありそうである)、まれに大会運営について不満が聞かれたりもした。世間の注目が授賞式のみに集中し、それ以外の重要な研究発表が十分な注目を浴びていないという批評もあった。しかし、参加者たちのほとんどは、フォーラムをたいへん楽しんでいたし、筆者個人も、アラブ世界内外から来た大勢の文学者たちと親交を結び、様々なテーマについて意見交換ができたという点で、まさに「出会いの場」という名にふさわしい貴重な機会であったと思う。たしかに、事前の準備は例によって慌しく、最終的な旅程が知らされるのは一週間前になってから、宿泊施設は到着後に、大会プログラムは前日になってようやく知らされるという状態であった。しかし、これも例によって、始まってしまえば何とかなるもので、特に大きなアクシデントもなく大会は順調に進んだ。また、ホストであるエジプト最高文化評議会から受けた懇待や細やかな気配りも印象的であった。この場をお借りして、関係者の方々に深甚なる謝意を表したい。
(2)カイロ滞在の後半は、主としてアメリカン大学の図書館で資料の閲覧や複写を行った。従来より、筆者は近代エジプト社会における衣装(特に男性の被り物)の変化に興味を持っている。そのような変化は──上述のスヌアッラー・イブラーヒームの新作のように──小説や自伝でも多々描かれている。これらの文学作品やその他の資料を通して近代のエジプト社会における文化変容の一端を探ることは、たとえば社会心理学的にも興味深いことではないかと考えている。今回は、上記図書館で主に20世紀前半の雑誌を閲覧して、このテーマに関する資料を集めた。さらに、カイロ大学文学部のアラビア語学科を訪れて、このようなテーマを含む様々な話題に関して研究者らと話し合ったり、研究セミナーを聴講したりした。また空き時間には、市内の書店で書籍を購入したり、書店主と懇談したりもした。
ところで、上記アラー・アル=アスワーニーは今、エジプトのみならず、アラブ世界でもっとも「売れている」作家である。昨年1月に出版された長編『シカゴ』にいたっては一年足らずのあいだに10回も増刷されている。ノーベル賞作家のマフフーズを軽く超えるような売れ行きである。『ヤコビヤン・ビル』は映画やテレビドラマにもなり、『シカゴ』も映画化される予定だという。前者はすでに19ヶ国語に翻訳されている(邦訳はまだない)。特に人気のあるのはフランスで、最近『アル=アラビー』誌に掲載されたインタビュー記事によると翻訳作品であるにも関わらず16万部も出たらしい。アラブ小説としては異例のことである。エジプト社会の暗部──政治的腐敗、宗教的急進主義(ジハーディストの作り方)、拷問、社会的不公正、同性愛にまつわる問題、人々の偽善的行為・言動など──を今まで誰もやらなかったほど赤裸々に描いたことが背景にあるのだろう。平明な文体を用いながら「宙吊り」を常用して読者に早く続きが読みたくなるようにさせたり、あけすけな性描写を行ったりしていることも、売り上げ増に貢献しただろう。『シカゴ』では、これらがさらにパワー・アップしている感がある。一言で言えば、確かに面白い。今まで小説など読まなかった人がアスワーニーを読み、かなり多くの人々が映画を観たらしく、数え切れないほど多くの論評がなされ、市井の人々の話題になった。「社会現象」と言われるゆえんである。
しかしその一方で、あれは文学の名に値しないとか、道徳的に問題である(映画版『ヤコビヤン・ビル』は「成人指定」になっている)とかいう悪評も多く、実際に人々はどのように受容しているのだろうかと気になっていた。もちろん、現代ではインターネットでかなりの情報を得ることもできるわけだが、今回の出張を機に、現地でいろいろな人々に感想を聞いてみた。ランダムに質問した上での単なる印象論に過ぎないことを断っておくとして、まず面白いという意見も当然ながら多い。しかし、とりわけ「文学界」では、慎重な意見やマイナス評価も聞かれた。いわく、手法面で特に新味はない、ジャーナリスティックな文体と内容である、文学作品として特に優れたものではない等々。さすがに「反道徳的」という意見は研究者からは聞かれなかったものの、手離しで褒める人はそれほど多くなかった。アラブ小説フォーラムでも、(筆者自身の発表以外で)まったく言及されていないわけではないが、特に大きな扱いを受けているわけでもなかったようだ(あるいはもう手垢にまみれたテーマということかもしれないが)。
批判的な意見にも一理はあるのかもしれない。だが、作者自身は上述の(かなり意地悪な)インタビューのなかで、もちろん反論を行っている。単純に言うと、そもそも平明な文体で書かれた面白い文学作品のどこが悪いのかということであり、悪評の背後にはかなりの「嫉妬」が混じっているというものである。そういうことも多いにありうるだろう。アスワーニーの作品をあまり積極的に評価しない人に対して、筆者は、それでもともかくエジプトの文学作品においてあれほどあけすけな政権批判ができる(あるいはそれが許される)ことはよいことではないか、と質問してみたが、複数の人から「単なるガス抜きに過ぎない」という感想を聞いた。無論、エジプトやアラブの評論家で彼を称賛している人も多い。近年おもしろい社会評論的エッセイを出し続けている経済学者のガラール・アミーンはその筆頭かもしれない。しかし個人的に強く感じたのは、ベストセラーにはよくあることだが、「文学界」における評価と一般的人気のギャップであった。
他方、外国では極短期間のうちに高い評価を受け、フランスやイタリア、ギリシア、オーストリアなどで数々の賞を獲得している。もちろん、小説作品として優れていると判断されたからこその受賞だろうが、外国人にとって特に興味深い作品であったことも間違いないだろう。湾岸危機の頃のエジプト社会を描いた『ヤコビヤン・ビル』もさることながら、『シカゴ』も2001年の9・11事件後の合衆国に暮らすエジプト人(とアメリカ人)を描いているという点で、まさに時事的な関心を呼び起こす。前作同様のテーマに加えて、ムスリムとキリスト教徒の両者を含めた在米エジプト人コミュニティにおけるアイデンティティの在り方についても考えさせられる。アメリカに同化する者、エジプトを忘れようとしてなお忘れられない者、いずれは戻る祖国における地位の向上のみを追及して、祖国の社会構造にがっちり組み込まれたまま滞米生活を送る者など、いろいろな人物が出てくる。異郷からエジプト社会を批判する者もいれば、(エジプトの)政権べったりの者もいる。その一方で、そもそもエジプトに関わろうとしない者もいる。あるいは、はなから非政治的な人物もいる。その合間に、純朴で宗教的な若いムスリム男女のラブ・ストーリーも展開する。基本的には合衆国という鏡を通したエジプト社会批判と言えるだろうが、ベトナム世代や黒人差別の問題にもスポットライトが当てられるなど、アメリカ社会に対する論評も行われている。そのようなところが、エジプトひいてはアラブ世界の政治や社会、またその対米関係などに現在的関心をもつ外国人の興味を特に惹きつけたのかもしれない。もっとも、今回出会った外国人研究者の一人は、やはり「文学的価値」に疑問符を付けていた。単に、日本で言うところの「純文学」と「大衆文学」の違いなのかも知れないが……
以上、報告というよりは気ままな雑文になってしまったが、出張中に頭をよぎったことも含めて書いてみた。(2008年3月31日)