刊行物
こちらでは東京大学フランス語フランス文学研究室の刊行物をご紹介しています。
研究室の所蔵資料をお探しの方は「図書の利用法」をあわせてご覧ください。
『仏語仏文学研究』
東京大学仏語仏文学研究会は1987年に『仏語仏文学研究』を創刊し、現在まで刊行を続けています。
本誌は、東京大学大学院人文社会系研究科・文学部フランス文学研究室の関係者 ― 教官、在学生、卒業生、留学生、訪問研究者 ― が、それぞれの研究成果を発表する場として構想されました。応募論文は編集委員会の審査・査読を経たうえで掲載されます。
『仏語仏文学研究』はUT Repositoryでご覧いただけます。
『仏語仏文学研究』は東京大学の学術機関リポジトリUT Repositoryで閲覧できます。各号は仏語仏文学研究会による刊行の後リポジトリに提供され、順次デジタル化されていくため、 リポジトリで閲覧可能な最新号と刊行済みの最新号は異なります。デジタル化前の最新号の閲覧や頒布をご希望の方は研究室までお問い合わせください。
UT Repositoryで読む
学術機関リポジトリ(Institutional Repository)とは、大学等の学術機関で生産された、さまざまな研究成果を電子的な形態で集中的に蓄積・保存し、学内外に公開することを目的としたインターネット上の発信拠点(サーバ)です。
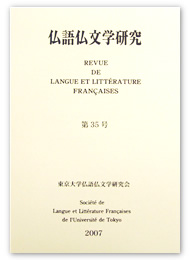
リポジトリに最近追加された論文
科学研究費補助金による研究成果報告書
『フランス近代詩とジャーナリズム』、2007年5月
(平成17‐18年度科学研究費補助金(基盤研究(C))による研究成果報告書)
研究代表者:中地義和
- 「はしがき」
- 海老根龍介 「「編集長精神」の時代の文学――ボードレールとジャーナリズム」
- Steve MURPHY, « Baudelaire et le temps du journal »
- 原大地 「書物と新聞、詩人と群衆――マラルメとジャーナリズムに関する一考察」
- 中地義和 「ラフォルグと『ラ・ヴォーグ』誌――自由詩の発生をめぐって」
- 前之園望 「アンドレ・ブルトンと雑誌『VVV』――「VVV宣言」精読」
- 本田貴久 「雑誌とミシェル・レリス」
『フランス文学における時間意識の変化』、2007年4月
(平成16‐18年度科学研究費補助金(基盤研究(B)(2))による研究成果報告書)
研究代表者:塚本昌則
- 「はしがき」
- 第Ⅰ部 〈文学〉とその外側――往還する時間のダイナミズム
- 鈴木雅生 「ル・クレジオにおける時間意識の変化――『三聖都』『砂漠』をめぐって」
- 田中琢三 「イデオロギー小説における時間――バレス『国民的エネルギーの小説』をめぐって」
- 新谷淳一 「古典主義・未開人・文学――人類の進歩と人文の顛末」
- 恒川邦夫 「クレオールの時間 《クレオール》の時間、《混成》の時間」
- 砂野幸稔 「西欧近代の〈時間〉と〈アフリカ文学〉の時間」
-
Tetsuya SHIOKAWA,
Kunio TSUNEKAWA, « Projection de Paul Valéry en Extrême Orient autour de son concept de temps » - Régine PIETRA, « Valéry, Dôgen, ou la vibration du présent »
- Hiroaki YAMADA, « La question du temps en psychanalyse et le cas d’Aurélia »
- Jacques LÉVY, « Temps, aspect et limite du discours narratif dans Miracle de Nakagami Kenji »
- William MARX, « Y a-t-il un temps occidental ? »
- Aymeric EROUART, « Aspects de la contestation chez Roger Nimier »
- Masanori TSUKAMOTO, « Mon Faust : l’instant et la répétition »
- 榊原哲也 「「時間は不動であり、しかも時間は流れる」――フッサール『内的時間意識の現象学』への一考察」
- 榊原哲也 「後期フッサールの時間論――「生き生きした現在」をめぐる諸問題」
- 第Ⅱ部 近代の二つの顔――〈前衛〉と〈後衛〉
- William MARX, « La littérature est-elle d’arrière-garde ? »(文学は後衛か?)
- Dominique CARLAT, « Comment écrire l’histoire des avant-gardes ? — Le cas de Pierre de Massot et de son panorama De Mallarmé à la revue dada 319, publié en 1922 »(いかにして前衛の歴史を書くか――ピエール・ド・マッソの『マラルメから「391」へ』をめぐって)
- 澤田直 「近代神話の裏面――サルトルにおける世代横断性」
- 野崎歓 「前衛と後衛の交わるところ――クロード・シモンをめぐって」
- 鈴木雅雄 「手紙が届かない――シュルレアリスムと通信メディアのパラドックス」
- 坂本浩也 「隠喩としての電話――プルーストとフロイトにおける無意識のコミュニケーション」
- 湯沢英彦 「「古きパリ」の誘惑――アルベール・ロビダとウージェーヌ・アジェ」
- 千葉文夫 「ロベール・デスノスとラジオ――『ファントマ幻想』以後」
- 永井敦子 「アンドレ・マルローと「革命」」
- 有田英也 「フランス知識人の後衛から――ドニ・ド・ルージュモンの『失業知識人日記』と『ドイツ日記』」
- 鈴木大悟 「ルネ・クルヴェルの革命論――「バルセロナ講演要旨読解」」
- 菅野賢治 「「時は起源を憎み、それでいて……」――クロード・ヴィジェ考」
- Georges SEBBAG, « Le temps sans fil surréaliste »(シュルレアリスムと無線的時間)
- 斎藤哲也 「引用のオートマティスム――『シュルレアリスム簡略辞典』を中心に」
- 岩切正一郎 「戸棚の詩学」
- 原和之 「ラカンのクロノ=トポ=ロジー」
- 守中高明 「ブルトンにおける〈近代〉――有限性の問い、偶然性の問い」
- 前之園望 「「松明を渡す」こと――アンドレ・ブルトンの「最初の透明者」」
- 大平具彦 「トリスタン・ツァラとプリミティヴ・アート――前衛を導いた二つの〈未開〉について」
- Michel JARRETY, « Valéry entre avant-garde et arrière-garde »(前衛と後衛のあいだのヴァレリー)
- 森本淳生 「交錯する前衛性と後衛性――ヴァレリーとブルトンにおける〈痕跡〉の問題」
- 塚本昌則 「ヴァレリーと反復――〈モーリーの夢〉をめぐって」
- あとがき1:塚本昌則 「近代の時間――〈後衛〉の視点から」
- あとがき2:鈴木雅雄 「モダンとポスト・モダンのあいだ――シュルレアリスムの視点から」
『聖域の表象と文学表現――新古典主義からロマン主義へ』、2006年3月
(平成16‐17年度科学研究費補助金(基盤研究(C)(2))による研究成果報告書)
研究代表者:田村毅
- 「はしがき」
- 荒木善太 「パリという庭――パンテオンと芸術の信仰」
- 田村毅 「ロマン派の夢と人類の叙事詩――ネルヴァル「オーレリア」草稿とマドレーヌ寺院の天井画」
- 吉村和明 「《暗殺されたマラー》から《トランスノナン街、一八三四年四月十五日》へ――絵画における〈現実的なもの〉」
- 保岡(田口)亜紀 「ネルヴァルの聖域、シテール島」
- 田中琢三 「ゾラにおけるパリ郊外――ノスタルジーとユートピア」
- 鈴木雅生 「ル・クレジオにおける空間の聖化――カオスからコスモスへ」
- 付録
- 「聖域の表象と文学表現 関係論文リスト」(鈴木雅生)
『フランス詩のフォルムの変遷とその文化的規定』、2005年3月
(平成14‐16年度科学研究費補助金(基盤研究(B)(2))研究成果報告書)
研究代表者:中地義和
- 「はしがきAvant-propos」
- 1. Autour des Fleurs du Mal
- Patrick LABARTHE, « Les Fleurs du Mal : un lyrisme crépusculaire »
- Shôichirô IWAKIRI, « Le notable poétique d’une voix »
- Makoto YOKOHARI, « L’hérésie et la longueur »
- 2. Le « petit poème en prose »et le « nombre »
- Jean-Luc STEINMETZ, « Sympathie, compassion et charité dans Le Spleen de Paris »
- Kazuaki YOSHIMURA, « Oeuvre sans nom : puissance et impuissance de la poésie dans les Petits poèmes en prose »
- Noriko SUGIMOTO, « La genèse romanesque du Spleen de Paris »
- Yoshikazu NAKAJI, « Recherche et rejet : l’autre dans Le Spleen de Paris »
- Antoine COMPAGNON, « La théorie baudelairienne des nombres »
- 3. Baudelaire le critique et sa postérité
- Patrizia LOMBARDO, « Baudelaire et le vertige du rire »
- Ryusuké ÉBINÉ, « Baudelaire et l’école réaliste : la liberté créatrice et son danger »
- Masanori TSUKAMOTO, « Les Paradis artificiels et Monsieur Teste : la théâtralisation de la conscience »
『近代フランスにおける神秘思想と文学』、2004年3月
(平成14年度~平成15年度科学研究費補助金(基盤研究(C)(2))研究成果報告書)
研究代表者:塩川徹也
- 「はしがきAvant-propos」
- Gérard Ferryrolles, « Pascal et les païens »
- Dominique Descotes, « L’interprétation des nombres chez Pascal »
- Ran-E Hong, « La superstition au Grand Siècle »
- 塩川徹也、「「われわれのみじめな正義」:原罪の「神秘」をめぐるパスカルとシャールの対決( « Notre misérable justice » : Confrontation de Robert Challe avec Pascal touchant le « mystère » du péché originel)」
- 付録Annexe
- 「近世フランス神秘思想関連文献リスト(Liste des ouvrages relatifs à quelques écrivains « mystiques » : XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles)」(田口卓臣)
『フランス近現代文学における眠りの表象』、2003年3月
(平成13、14年度科学研究費補助金(基盤研究(C)(2))による研究成果報告書)
研究代表者:塚本昌則
- 「はじめに」
- 本田貴久 「ミシェル・レリスの半睡の場――夢の記述から夢による記述へ」
- Taichi Hara, « Entre la nuit et le jour : introduction à l’étude du rêve dans Les Chants de Maldoror »
- Masanori Tsukamoto, « Les traces d’un autre――Le rêve et le langage dans les Cahiers de Valéry »
『断章形式の詩学と人間学―モラリスト文学再考』、2002年3月
(平成12年度~平成14年度科学研究費補助金(基盤研究(B)(2))研究成果報告書)
研究代表者:塩川徹也
- 「はしがきAvant-propos」
- (国際セミナー「断章形式の詩学と人間学―モラリスト文学再考」Poétique et anthropologie du fragment : Moralistes reconsidérés)
- Tetsuya Shiokawa, « Ouverture »
- Louis van Delft, « La poétique du fragment chez les moralistes classiques »
- Nicole Celeyrette-Pietri, « Pratique du fragment chez Paul Valéry : la pensée, l’écriture »
- Jean-Christophe Devynck, « Fragments et séries neutres dans la Jalousie d’Alan Robbe-Grillet »
- 付録Annexe
- 「本研究のためにフランス国立図書館からマイクロフィッシュで取り寄せた文献リスト(Liste des ouvrages acquis sous forme de microfiche pour ce projet de recherche)」(永井典克、辻部大介)
『フランス文学における「モダン」の歴史的研究』、2001年3月
(平成10、11、12年度科学研究費補助金(基盤研究(B)(2))による研究成果報告書)
研究代表者:中地義和
- 「はじめに」
- 辻部大介 「ラ・モットのオード論――18世紀初頭〈モデルヌ〉の詩学」
- 吉村和明 「白鳥――ひとつのイメージ」
- 中地義和 「憐れみと詩――『パリの憂愁』の存在論」
- 鈴木啓二 「ボードレールとエネルギー」
- Jean-Luc Steinmetz, « Le Génie de l’enfance »
- James Lawler, « Autogenèse »
- Laurent Jenny, « Henri Michaux : gestes simples »
『フランス近現代文学における「夢の詩学」』、2000年3月
(平成10、11年度科学研究費(基盤研究(C)(2)による研究成果報告書)
研究代表者:塚本昌則
- 白井恵一 「『シルヴィ』における夢と人生のアイロニー」
- 後藤敏郎 「闘いとしての不眠――『マルドロールの歌』における夢と現実」
- 福田耕介 「死を見つめる母親――フランソワ・モーリヤック晩年の夢」
- 塚本昌則 「ヴァレリーと夢の詩学――「放心のデッサン」をめぐって」
『フランス文学における「私」のディスクール』、1999年3月
(平成8,9,10年度科学研究費(基盤研究(B)(2))による研究成果報告書)
研究代表者:田村毅
- 月村辰雄 「イエズス会のレトリック教科書 1.ソアレスの『修辞学』」
- 藤川亮子 「「疎外されるわたし」の演出へ――12~13世紀の抒情詩における「わたし」の言説とその変容」
- 大久保康明 「モンテーニュにおける探求する「自己」の表象」
- 佐藤淳二 「「私」・「ディスクール」・「真理」――ルソーにおける自伝的テクストのプロブレマティック」
- 後藤敏郎 「主人公の誕生 『マルドロールの歌』「第二歌」を通して」
- 久木田英史 「プルーストの文章」
- 福田耕介 「憎悪の死と蘇り――『蝮のからみあい』における「私」の二重性」
『規範から創造へ――レトリック教育とフランス文学』、1997年3月
(平成6・7・8年度科学研究費(基盤研究(B)(2))による研究成果報告書)
研究代表者:塩川徹也
- 月村辰雄 「プロギュムナスマタの西漸」
- 横山裕人 「学校とレトリック:19世紀フランス中等教育の場合」
- 辻部大介 「推論から論証へ:モンテスキュー『パンセ』の一つの読み方」
- 朝比奈美知子 「ネルヴァル、ノディエ 自伝的エクリチュールにおけるディグレッション」
- 沢崎久木 「『ボヴァリー夫人』と『ルチア』」
- 加川順治 「アンチ・レトリスムとプルーストの創造」
- 生方淳子 「歴史学の言説における「私」:セルトー、ヴェーヌ、サルトル、フッサールを手がかりに」
- 吉川一義 「プルーストとモロー:文学と絵画の修辞学」
『レトリックとフランス文学――伝統と反逆』、1994年年3月
(平成5年度科学研究費(一般研究B)による研究成果報告書)
研究代表者:塩川徹也
- 月村辰雄 「プロギュムナスマタ――ある修辞学の練習問題集をめぐって――」
- 中地義和 「アニミスム ディナミスム――ランボーの“レトリック” ――」
- 高原照弘 「フランス18世紀におけるレトリック」
- 横山裕人 「フランス19世紀におけるレトリック――理論と実践――」
『フランス文学におけるパリ――中世から現代まで』、1994年3月
(平成4・5年度科学研究費補助金総合研究(A)研究成果報告書)
研究代表者:田村毅
- 田村毅 「ヴィエイユ=ランテルヌ通り4番地――ネルヴァル神話の誕生」
- 吉田城 「プルーストの見た戦争下のパリ――『千一夜物語』の世界」
- 有田英也 「セリーヌの郊外――人生ゲームとしての『なしくずしの死』」
- 別冊
- 『年譜 ジェラール・ド・ネルヴァル――作品・記事・書簡 総目録』(田村毅・梅比良節子・丸山義博・村松定史)
『フランス文学における旅の観念と世界像の変容――関連文献目録(データ・ベース)作成と作品の研究』、1991年3月
(平成1・2年度科学研究費補助金一般研究(B)研究成果報告書)
研究代表者:田村毅
- 田村毅 「ネルヴァルのウィーン幻想」
- 野崎歓 「ネルヴァルと<東方紀行>の系譜」
- 有田英也 「未開と詩神――アンリ・ミショーとミッシェル・レリスの旅行記における脱西欧の志向」
- 小倉和子 「プレザンス探求の旅――イヴ・ボヌフォワの詩的地理学」
『詩学・修辞学・批評――フランスにおける文学観の変遷』、1989年3月
(昭和62・63年度科学研究費補助金一搬研究(B)研究成果報告書)
研究代表者:二宮敬
- 月村辰雄 「平韻八音綴詩句の詩法――マリー・ド・フランスと12世紀後半の新傾向」
- 塩川徹也 「レトリックと文学史――『プロヴァンシアル』第11書簡をめぐって」
- 田村毅 「ネルヴァルの初期詩篇――19世紀・王政復古期の文学の一形態」
- 小倉孝誠 「オーギュスタン・ティエリにおける歴史叙述の詩学と論理」
- 吉村和明 「批評と死の体験――ボードレールにおける批評と詩学」
- 中村俊直 「ポール・ヴァレリーにおける「至高の愛」の理念――『我がファウスト』の『リュスト』の劇の読解を中心として」
