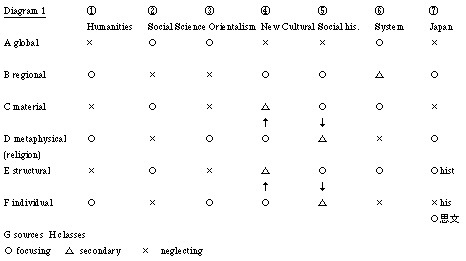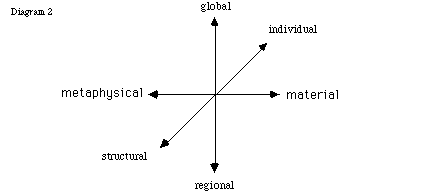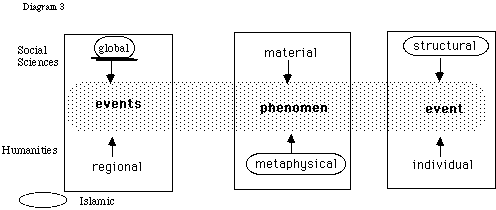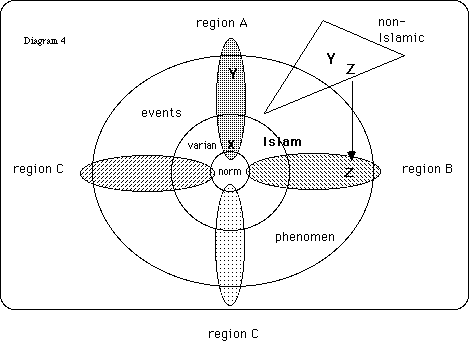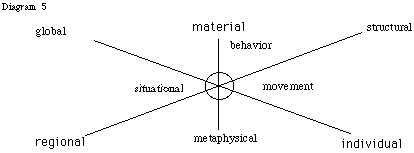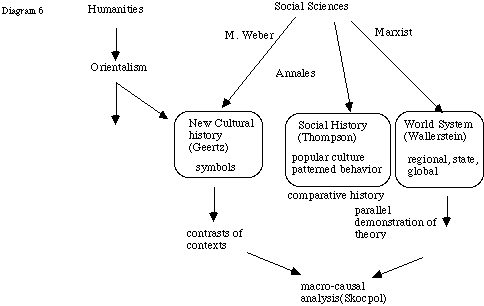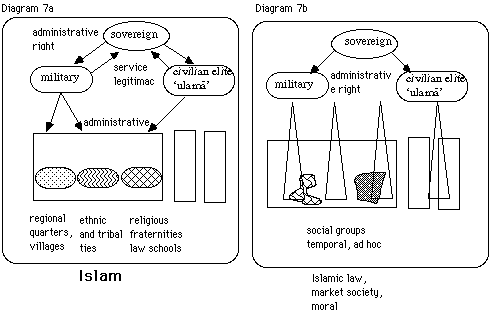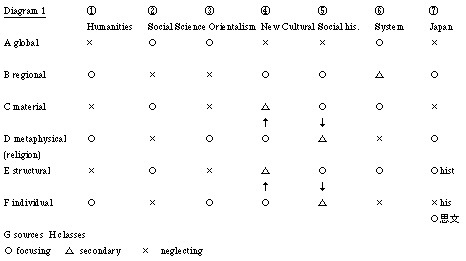
日時:1997年10月25日(土)
場所:中近東文化センター第2会場小講堂
開会の辞:後藤 明
趣旨説明:小松 久男(司会)
基調講演:「地域研究という第三の道」
三浦 徹「歴史学の側から」
長沢 栄治「社会科学の側から」
コメンテーター:モジュタバ・サドリア、加藤 博、林 徹
イスラーム地域研究(文部省科学研究費創成的基礎研究)
後藤 後藤でございます。いま日本オリエント学会の常務理事という立場を仰せつかっておりまして、その立場から一言ご挨拶を申し上げます。今回は第39回の日本オリエント学会の大会でございます。恒例ですと、だいたい1日目は公開講演ということになっておりますが、実行委員会委員長三笠宮殿下をはじめ、実行委員のメンバーの方々が講演会ではなくてフォーラムという形で、日本のオリエント学について自由に語って、将来を展望したいという強いご意志がございまして、このような形でフォーラムが設けられたのかと思います。
オリエント学という学問はどのような領域を指しているのかということはいろいろと問題があるかと思いますが、私が理解しますには、「オリエント」という地域に関する学問で、われわれがそう呼ぶ地域は、ここの会場は中近東文化センターですが、中近東、ないしは中東と呼んでいる地域とほぼ重なるのではないのかという気がいたします。
しかし、現代の日本語でオリエント学、あるいはオリエントといいますと、何となく古い時代、イスラームをカバーしないもっと古い時代の学問をさすというイメージがないわけではないのだろうという気がいたします。しかしイスラーム以前のすべてかというと、必ずしもそうではなくて、紀元前4世紀ですか、アレクサンドロスが征服して以降のいわゆるヘレニズム時代、あるいはローマの時代というのはあまりオリエント学の対象になっていないような印象がないわけでもないと思います。
しかし、対象とする地域がいわゆる中近東、中東と重なるとすれば、それは歴史が紀元前で消えているわけではなくて今日まで続いているという意味では、何となくイメージされる古代オリエント学からヘレニズム時代、ローマ時代、そしてイスラームの時代へと続く大きな時間の流れを私たちは考えなければいけないのだろうという気がするわけです。
最初は、三笠宮殿下をはじめ実行委員の皆様方は、そのような意味で古代オリエント学とイスラーム世界研究を区別せずに一つのフォーラムで中近東、オリエントという地域を取り上げようというご意向があったような気がいたします。しかし現実はオリエント学の研究者とイスラーム時代の研究者の対話が成り立ちがたいということで、このような二つのフォーラムという形になったかと思います。将来は一本化されて、一つの地域を非常に古い時代から現代まで通して研究して、そして新しい地域研究の展望を開いていくのだという立場もまた必要かと思います。そのような意味でいずれは二つのフォーラムではなくて一つのフォーラムとして語り合う時代が来るのではないのかという気がいたしております。とりあえず今回はイスラームの時代に限って、タイトルとして「過去から未来のイスラーム地域、その広がりと深まり」と題しますフォーラムを始めさせていただければと思います。
なお、このフォーラムは、「イスラーム地域研究プロジェクト」という、佐藤次高先生を中心として始まったばかりの地域研究プロジェクトがございますが、それとの共同の主催ということになっております。よろしくご議論をお願いしたいと思います。一言ご挨拶を申し上げました。失礼いたしました。(一同拍手)
川床 では、後は小松先生、お願いいたします。
司会(小松) それではただいまから、フォーラムを始めたいと思います。まず、このフォーラムの趣旨について、お話をしておきたいと思います。このタイトル並びに今回のフォーラムの陣容を考えられたのは、今年の4月から開始された「イスラーム地域研究」と題する研究プロジェクトのリーダーであります佐藤さんと中近東文化センターの川床さんのお二人であり、私はその概要が決まったあとで司会をするようにと頼まれました。私自身は、実は日本オリエント学会の会員ではありませんので、(一同笑い)それを理由に硬くお断りしたのですが、このフォーラムは公開講演である、したがって会員でなくてもよろしいという、大変開かれた学会の精神にどうも太刀打ちすることができず、このようなことになりました。
さて、私自身は、「過去から未来のイスラーム地域」というタイトルについてあまり深い理解はありませんけれども、私なりに解釈しますと、このようなことになるだろうと思います。
今回のフォーラムの後援団体が「イスラーム地域研究」という研究プロジェクトでありますように、今回のタイトルはそれとの関連で考えられたのだろうと思います。その副題には「広がり」と「深まり」という二つの言葉が書いてあります。まず、その広がりという言葉について考えてみましょう。今回のプロジェクトの対象とする地域は大変広い地域にまたがっています。それは、歴史的に見ても現在においても、いわゆる中東・イスラーム地域に限定されず、世界各地に居住しているムスリム集団に着目し、彼らが作り出しているいろいろな問題をすべて対象にしようという立場です。ですから、例えばEUの中にいて生活し働いている、トルコ人の労働者の問題、あるいは中国の中に居住するムスリムたち、もちろんアメリカ大陸も含まれますけれども、そのような世界の各地に展開しているムスリム集団を相手に考えていこうという広域的な問題の設定というところに特徴があります。
次に「深まり」ということです。今回のプロジェクトは、文部省に提出された正式なタイトルでは「現代イスラーム世界の動態的研究」となっていますが、それを端的に表現する言葉として「イスラーム地域研究」という言葉が考えられました。そのタイトルが象徴していますように、今回はさまざまな伝統的なディシプリンをもった人々の共同作業を行うわけですが、その際にやはりいろいろな意味でこれまでの殻を破って出ていくというところに力点がおかれています。
それによって、実に多様で複雑なムスリムをめぐる諸問題を研究する基本的な姿勢や立場というものが生まれてくるだろう、やや誇張していえば、挑戦する姿勢、それによって研究が深まるということを想定した言葉だと私自身は理解しています。
そして「過去から未来」という言葉ですが、いま申しました伝統なディシプリンからの脱却というか、殻破りというような側面もありますし、さらに今回のプロジェクトはたまたま20世紀から21世紀へというちょうど5カ年の計画なのですが、そのプロジェクトが終わるのが2002年、ちょうど新しい世紀の出発点に当たり、そこからまた新たなイスラーム地域研究が展開していくだろう、そのようにしてみたいという願いが込められているように思います。
あるいはこのような解釈は、フォーラムの企画をされたお二人のお考えとは異なるかもしれませんが、今日、司会をお引き受けするに当たって、私の理解をお話しすると以上のようなことになります。川床さん、これでよろしいでしょうか。
川床 結構です。
司会 了解が得られましたので、このまま続けることにいたします。さて、今日はプログラムにありますとおり、大変多くの方々に講演とコメントをお願いしていますが、林さんを除いて皆さんこのプロジェクトのメンバーということになります。まず三浦さんに、人文科学の立場からの方法論について、それから長沢さんには、社会科学側からの問題提起をお願いいたします。そのあとコメンテーターとしてモジュタバ・サドリアさん、加藤博さん、林徹さんの順番でお願いをします。いずれの方々も政治学、国際関係論、あるいは歴史学、さらには言語学といったディシプリンを背景に、しかしそこから新たな挑戦を現在果敢に実行されています。それから、プログラムには記されていませんが、このコメントの3番目の林さんのあとに、たまたま今回のプロジェクトでアメリカからお招きしているHumphreysさんというイスラーム史の研究者の方がここにお見えですので、事のついでといっては何ですが、アメリカにおけるイスラーム史研究の現状について短いスピーチをお願いしようと思っております。
では、時間も来ましたので、最初に三浦徹さんから、お手元にあるレジュメに沿って、地域研究への新しい問題提起、提言をお願いしたいと思います。三浦さん、よろしくお願いします。
三浦 ご紹介いただきましたお茶の水女子大学の三浦です。私自身はアラブの中世史を専門としておりますけれども、いまのプロジェクトの中で事務局のような仕事をしております関係で、「イスラーム地域研究」の方向を論じるなどという難題を引き受けてみることになったわけです。きょうのテーマでは、どうしても研究の方法のような議論が多くなると思います。すると、「そのような抽象的なことをいくら議論しても研究が進むわけではない、大事なことは史料に向かうことだ、データを分析することだ」というお考えの方も恐らくいらっしゃると思いますし、そのようなお考えの人は、このシンポジウム自体に参加されていないかもしれないわけですが、私自身は、そのような批判があることを理解した上で、研究の方法を議論するということには意味があると考えています。それは日常的に史料に向かっていまして、どのように史料に語られている事実を読むのかというときに、やはりいろいろな方法を使ってみないと解けないことがありまして、史料をとにかく何時間でも読んでいるのが楽しいということでないかぎり、方法の問題は皆が共通に考えていくべきものだろうと思います。
それからもう一つは、かなり多くの方が大学というようなところに所属されていて、要するに研究だけをやっていればいいということではなくて、教育ということが任務になっている。昨今の情勢からして、教育というウエートがどこの大学でも非常に高くなっている段階で、学生、あるいは大学院生たちとどのように接していくのかというとき、やはり自分の集めてきた事実をどのように整理するのかということは、これまた日常的に問われている問題だろうと私は考えております。その意味で、きょうのシンポジウムは自分にとってもいい機会だと思って引き受けさせていただきました。
レジュメとして、あまり整理し切れていないものをそのまま用意しておりますが、日本語で書いてある部分が3ページと、英語で図表(diagram)を7つほど書いたものがございます(図は末尾に掲載)。両者は、対応していまして、図表をみながら議論を整理していくというやり方をしたいと思います。図表を英語で書いたのは、アメリカからHumphreysさんがお見えになられて、ちょうど今週の火曜日に”Tradition and innovation in the study of Islamic history"という題で講演をしていただきました。Humphreysさんがお見えになるということを意識して、また利用した文献が英語であったので、そのまま主に英語で起こしていったというのが、理由であります。
1)中東地域研究
私のほうは人文科学からの問題提起ということですが、自分のなるべく専門領域に即して歴史学ということから地域研究、あるいは総合的、超域的interdisciplinaryな研究がどのような点で可能であり、問題があるのかということに絞って考えてみました。
まず、地域研究、特に「中東地域研究」という言葉を聞いて思い出すのが、Hamilton A.R.Gibbが1963年に発表した『Area Study Reconsidered』という文章で、これは『みすず』(8:3-4号、1966)で林武先生が翻訳されていて、そのような古証文をつい思い出して引っ張ってきました。ギブ自身は、いわゆる伝統的な東洋学、オリエンタリスティークの学者でして、そして戦後ハーヴァード大学に中東研究センターが開設されるにあたって、アメリカに招聘された。その経験から地域研究のあり方を論じた、英国での講演の記録になります。そこでギブは「東洋学と社会科学との結婚ということが地域研究の課題である」とまとめています。「結婚」というのは何と何が結婚するのかということが問題になるのですが、ここでは当該の地域について、ここでいえば中東についての、firsthandな知識、特に言語の能力・知識を持った人間--これは主に東洋学が育成してきた人間だと思いますが--そのような能力を持った人間が、同時に社会科学の専門能力を持たなければいけない、そうでなければ地域研究は発展しないし成立しないと述べています。
社会科学の専門能力とは何かといいますと、それは社会科学が持っている分析方法ということで理解していいのではないか。なぜ、伝統的な東洋学の畑にいたギブがそのようなことを言い出したのか。その理由はとても全部は紹介できないのですが、非常に単純にいってしまえば、東洋学、あるいはイスラーム史ということに手を染めている研究者が集めてくる個別的な事実、その個別的な事実をいくつか編年順に並べて、ある事象の原因は何であるとかんであるといっていることは、社会科学をフィールドにしている人にとっては、お笑い草である。単線的な事実の集積で、どうして論証になるのかという社会科学者の批判をちゃんと受けとめなければいけないというところにあります。私自身は東洋学の畑におりますので、そのような受け止め方をいたしました。
そこで、先ほどいったようにギブは、社会科学と結婚しなければいけないと主張するわけです。ちょっと横道にそれますが、結婚をちゃんとさせなければいけない理由はといいますと、地域研究という学部とか、学科がいまアメリカにもできていて、そこで学生を育てている。そこで地域研究の方法を確立しなければ、そのあと研究でもフィールドでも受け入れられない、中途半端な人間を育ててしまうことになる。言葉は適切ではないと思いますが、「不義の子」になってしまう、という危機感を表明しておりまして、これもわれわれの日本の現在の大学の実情、国際何とか学部などという名前が増えてきている現状の中で、決して笑える問題ではないと思います。
ところが、その結婚はアメリカでもうまくいっているのか、というとそうではない。そこで原因はどこにあるのかということを考えてみました。ここでレジュメの1−・のところに入りますが、それは人文学と社会科学というものが持っている個性がそもそも違うのではないのか。やはり人文学というのは、個別の地域とか、個別の人間、それは君主であれ、文学者であれ、宗教者であれ「個人」にこだわっていく、そしてその人たちをできるだけ内在的に、すなわちその人の残した言葉、言語、テキストで理解していくという伝統があると思います。
これに対比して申し上げれば、社会科学というのは、むしろ基本とするモデルは、具体的な個人ではなくて抽象的な個人ではないか。そしてその抽象的・一般的な個人からスタートして社会のモデルを作り上げていく、その意味では普遍的なモデルを志向することになります。そして社会のモデルを作っていく場合に、非常に重視されるのが因果関係ということになるのではないのかと思います。
これは、もう少し別の例を挙げて申し上げれば、たびたび引用されるEdward Saidの『オリエンタリズム』がございます。これは伝統的なヨーロッパの東洋学の批判ということでよく知られた著作ですが、もう一つ注意しなければいけないのは、このサイードが著作の最後のところで、ではわれわれはいかにしたら異文化認識が可能であるのか、どのように、中東なり、イスラームなり、他地域を見たらいいのかというときに、肯定的に評価している研究者が何人かおります。それはそこに挙げましたM.Rodinson、Abdel-Malek、Roger Owenになるわけですが、いずれも社会科学者、社会科学の領域にある人間であります。そしてサイードの議論は、世界を東と西とに分かつ、東洋と西洋に分かって、そこには本質的な区別があるという議論を「オリエンタリズム」と呼んで批判したわけでありまして、その逆の立場に立てば、東と西には同じ人間がいる、人類は同じ人間なのだという意味で、普遍的な人間というところをスタートにする点で、社会科学者の仕事を評価しているのではないか。先に挙げられた研究者の仕事には、私は好きになれないものもあるのですが、そのようにサイードの議論を理解することができるのではないかと思います。
ところが逆に、社会科学に対する人文学の批判もあります。それは社会科学というのは、高々西洋近代に生まれた一学問方法に過ぎない。ですからその意味では近代ヨーロッパのローカルな学問である。それが普遍的なものだと考えるところに問題があるという議論も可能であると思います。あるいは実際にそのような声が時折聞こえてまいります。
いまのように両者の溝はかなりあるということになりますけれども、では、われわれ日本の中東・イスラーム研究、特に歴史研究の中では、その問題はどのようになっているのか。まず、ここ20年の非常に顕著な動向は、「現地主義」という言葉で表した人がいますが、現地の言語で学ぶ、留学するなら現地へ行くことがかなり際立った特徴です。他の分野では米国に留学したりするわけですが、現地へ行くということを非常に重んじている。そしてイスラームというものを内在的に、あるいはイスラームの歴史というのを内在的に理解するということを非常に重視しておりまして、その成果かどうかわかりませんが、最近では世界史を語ろうとする場合に、イスラーム世界ではどうですかということを必ず誰かが問題にするようにはなってきています。
ただし、それの裏返しとして、他分野との交流が、かつてよりもむしろ減ってきている。そして「イスラーム世界では、こうです」というと、「あ、そうですか」と納得してくれる人が増えたお陰で、われわれはそれ以上説明しなくてもすむようになってきている。その意味で、そこに書きました「イスラーム史は世界史の蚊帳の外か」というのは、たとえばかつては、封建制であるとか、近代化であるとか世界史上のタームの中でしか、イスラーム地域が相手にされなかったの対して、独自な世界として把握されるようになったという点ではプラスであると思うのですが、逆に世界史のいろいろな流れの議論とうまく接合しなくなってきている。言葉をかえていえば、普遍性を失いつつあるという問題があるのではないのか。これが、私たちのいまの日本の中東・イスラーム研究の一つの問題ではないのかと思います。
それがただ日本だけの問題ではなくて、先ほどに Humphreysさんの講演の中でも、米国の中東研究においても、いまの歴史学のさまざまな潮流、アナール派の流れであるとか、世界システム論であるとか、いろいろなものがあるわけですけれども、全体として米国においても中東研究は、そのようなものとはちょっと袂を分かっている、「隔絶されているisolated」という言葉を使っていましたけれども、そのような傾向が米国においても見られる。その意味では、「蚊帳の外」という状況は、日本だけの現象ではないと理解いたしました。
2)方法の比較
そこで、2の「方法の比較」に入りますが、ここでは、社会科学と人文学、あるいはその中での一つの顕著な傾向を持つオリエンタリズムという三つの研究領域に加えて、最近の歴史学の中での新しい潮流、すなわち、・の文化史的な傾向を強めている流れ、・の社会史というか、社会運動史的な流れ、そして・の世界システム論を含めて、その違いというのはどこにあるのかということを考えてみたわけです。
これは到底、私一人のちっぽけな頭で考えられることでありませんで、実は参考文献にありますように、すでにいくつかの議論がありまして、近代史を専門とするEdmund Burkeとか、中世史のLapidusであるとか、あるいは近代史のHouraniであるとか、中東研究と最近の歴史学の潮流について議論した論文も参考にしながら、整理を試みてみました。
図表の1から3をちょっとご覧いただきたいと思います。いちいちは触れませんが、まずこの表の見方をご説明したいと思います。まず、研究対象に対するアプローチの仕方を、3組にわけて整理してみました。これはいずれも主に歴史の分野を想定して考えております。一つは、ある事象を見る場合に、非常に世界大的な、グローバルな見地から説明しようとする立場(A)とregionalな、地域的な立場を重視する立場(B)があるのではないのか。この二つABがセットになります。2番目は、material (C)とmetaphysical(D)と呼んでみましたが、物質的な条件というものを重視する、これは社会経済史学などの一つのスタイルですが、それに対して宗教に代表されるmetaphysicalなものにウエートを置いていくというアプローチの仕方があるのではないのか。
それからEとFというのは、社会というものを考える場合に、個々人ではなくて、全体的なシステムとか、構造などの存在を前提にして考えていく立場(E)と、システムよりは、個々人の側から個人を重視してアプローチしていく立場(F)という二つがある。そして図表1の横軸にあるそれぞれの学問領域や最近の潮流について、○とか×とかを書きましたのは、それぞれが、A、B、C、D、あるいはE、Fのどちらにウエートを置きながら進められてきたのかということについての、私の判断を示したものです。
新しい潮流(・、・、・)のところに、いずれも△印が付いているのは理由がありまして、その両者の存在を前提にしながら、すなわち片方を無視するのではなくて、どちらか一方に重きをおきながら他方へとアプローチしようというスタンスを表しています。たとえば、Cultual Historyといわれる領域では文化の問題から社会的な、たとえば経済的な取引というものを解析していくというアプローチ、逆にSocial Historyと書いたところは、物質的なものを扱いながら、あるいは労働運動であるとか、民衆暴動などを扱いながらそのバックグランドにある文化的な意識、モラルであるとか、そのようなものを析出していくという意味で、そこには△印を付してみたわけです。あるいは世界システム論についても、globalな観点とregionalな観点を接合させていくというところに意味があるとすれば、やはりそこにも△印が付くのではないのかと考えました。
そしてこれらの3組に分けられた要素を、図表2のように三つの座標軸に表現するとすれば、それぞれの学問領域や個別の研究は、アプローチの仕方に強い弱いがありながら、三次元の8象限のどこかに位置づけられることができるのではないのかという意味であります。
6つの要素というのはアプローチの仕方であるといいましたが、図表の3のところでは、それがぶつかってくる場面、たとえば地域的な利害とグローバルな利害がぶつかってくるところに事件が生じる、あるいは構造と個人がぶつかるところに事件が生じるということを示しています。そして、われわれが、実際に研究をする場合には、事件とか、現象という形で史料に現れてきたものを手がかりにしてアプローチするわけで、その接近の方向が6種類あるということを示したわけです。
この図を使って整理すれば、このグルーピングの中の上の領域、たとえばglobal、material、structuralのほうに足をおいているのが社会科学であり、regional、metaphysical、individualなものに足をおいているのが人文学のほうではないかと整理できると思います。
この図を書きながら気づいた問題というのは、第一に、この3組の領域がバラバラにアプローチされているということです。構造的なものと個人的なものを扱っている人はそこだけに目が行き、他の要素を顧慮しなくなるという問題があるのではないのかということが一つです。
その時にもう一つ問題として提起したいことは、そこに「Islamic」という丸が囲ってあります。これは、「イスラーム」というふうにわれわれが一般に呼んでいるものは、この要素分けでいくとどのようになるのか。もちろん常識的にmetaphysicalなものであろう。そしてある構造を持ったものであろう。そしてglobalなものというのは地球全部ということではありませんが、個別のregionalを越えて存在すると理解されている。ですからIslamicとわれわれが呼びたいものは、社会科学、あるいは人文学の通常のセットとは違うセットになっているのではないのかということに気付くわけです。するとイスラーム研究、あるいはイスラーム史研究がなかなか個別の、いままでの学問の disciplineの中に入りきれない一つの理由は、この「ねじれ」に一つの原因があるのではないのか。そしてこのねじれをどのように解決するのかということが、問題になるのだと思います。
次に、これに関係して図表の6をご覧いただきたいのですが、これは先に図表の1で取り上げた研究領域を、時間軸の流れで整理したものであります。これをいちいちご説明する余裕はございませんが、問題として提起したいところは、歴史学の新しい領域として出てきている文化史、社会史、世界システム、この流れがそれぞれ社会科学と人文学の方法の革新として出てきたものであることを示すことが、このチャートの狙いの一つであります。
それぞれはどのような領域を開拓しているのかというと、いま分けましたファクターの境界になる部分が、あるいはクロスする領域が主張されている。たとえば文化史の中では、よく引用されますが、Clifford Geertzの「symbols」、文化というものを、単にmetaphysicalなものだけではなく、広く考える。例えば、社会階層でいえば、 high-cultureだけではなくてpopular-cultureも含めて考える。あるいはテキストに書かれたものだけではなくて、書かれない資料も含めて考えていく、というようなものが境界領域として照準が当てられている。あるいは社会史と呼んだところでは、先ほどいったように、暴動なら暴動の背景にあるようなpatterned behaviorといいましたけれども、ある共通の行動様式というものを抽出しながら、そこからカルチャーに接近していくという、要素の接点にある部分を照準にしてきているのが新しい歴史学の流れではないのかと思うわけです。
3)比較の必要
3番目に、この図の中で考えたいこととして、いずれもが比較史comparative historyというものを、どこかに内包しているところがあります。そして、それは、レジュメに名前を挙げましたスコチポルSkocpolという研究者、これは歴史社会学という領域の研究者ですが、彼女が比較史の方法に関する論文で行っている、比較史の3つのタイプに相応していると思います。
まず「文化史New Cultural History」と呼んだものは、それぞれの地域には地域の個性、固有性、文化のコンテキストがあって、それを全体として引っ張ってくることに重点がある。ではなぜそれが比較ということに関わるのかというと、それは比較をしてみなければ、どれが地域の個性か当然わからないわけでありまして、これは一見一つの地域の中にわけ入っていく作業でありながら、同時に外との比較をしなければ出てこない領域になってくるわけです。
次に、世界システム論は、Skocpolの用語でparallel demonstration of theoryと呼んでいるものに対応するのではないか。これはわかりにくい英語ですが、私の理解では、「ある一つの歴史的な現象はパラレルに現れてくる。それは共通の因果関係があるからだ」という立場であります。だからこれはかつてのマルクス主義歴史学と考えていただいても結構ですけれども、一般的な一つの歴史法則があって、それが個別の領域に現れてくるという立場であります。それは当然世界史的な視野を持っていなければ、理論は確立されないし現象も説明できないわけで、その意味で比較を当然のことながら必要としている。これは社会科学でいう比較と考えていただいても結構だと思います。
そしてこの両方の特徴を生かした第三の道として、Skocpolが提唱しているのが、「Macro-causal analysis」と彼女が呼んでいるものであります。これもなんか厄介な用語であるのですが、読んでみればそれほど難しいことではなくて、日本語では「歴史における因果規則性を分析する」と書きましたが、それぞれの地域の歴史事象を検討するさいに、客観的、科学的であるためには因果関係というのをもう少しきちんと突きとめる必要があろう。そして因果関係というのは、当該の地域の現象だけを追っていたのでは説明できない、比較が必要になるという議論であります。
これをもっとわかりやすいことでいえば、マルク・ブロックの『比較史の方法』にある議論でありまして、マルク・ブロックの引いている例でいえば、Xという現象がある地域にある。そしてそれが原因となって、Yという現象が生まれたという仮説を立てる場合に、それがいかにもっともらしくても、ほかの地域の事例を検証しなければ成立しない。すなわちXがあっても、Yが生じないという地域があったら、それが十分な立証とはいえないであろう。あるいは逆にYがあっても、原因たるXがない地域の事例が出てきたとしたら、仮説は成立しないだろう。非常に単純な問題提起ですが、Skocpolがいっている問題は、ある地域の事象を説明しようとする場合に、それは当然比較ということの手続きを取らなければ説明し得ないということであります。
いまのマルク・ブロックであれ、Skocpolの議論であれ、痛いところをつかれたという思いがします。私も中世史などというたいへん資料の少ないところをやっている人間でありましては、たとえば、エジプトのマムルーク朝期、とくに14世紀の繁栄や都市の発展ということがいわれるわけですが、その原因はなにかと聞かれると、例えば東西交易であるとか、検地による全国的なイクター制の確立ということが挙げられるわけです。それはエジプト史という枠の中だけを見た場合には、確かにエポック・メーキングであって繁栄の原因として理解されるかもしれない。しかし、いまのマルク・ブロックの議論を援用するのであれば、例えばマブレブでは同じような繁栄が同時期になかったのかどうか。あるいはイクター制であれ、東西交易であれ、同様の現象がみられる地域をとって、そこはどのような歴史のたどり方をしたのかということを検証してみなければ、確かに両者に因果関係があるとはいえないのではないのかという反省が自分の中にはあるわけです。
4)中世イスラーム国家論の構造
ここで、自分のフィールドである中世のイスラーム国家の構造論というものに即して、いまの議論を検討し直してみたいと思います。
中世のイスラーム国家論、これは発表要旨にも書きましたけれども、一つの共通の構造といっていいようなものが、措定されているように思います。先ず社会構成においては、モザイク的な社会がどうもベースになって考えられる。これは図表の7aというのが、どちらかというと伝統的な中世イスラーム国家論の構造であります。7bというのが、それを何とか書き換えたいという私のはかない望みを表した図表であります。
モザイク社会というのは、一番上に君主がいて、スルタン(sultan)と呼ばれようが、マリク(malik)と呼ばれようが、シャー(shah)と呼ばれようが、イマーム(imam)と呼ばれようが、それは同じであると考えております。そして社会的なレベル、1番下のレベルでありますが、ここにはさまざまコミュニティーがある。街区であり、あるいは宗教的なフラタニティーであり、あるいはエスニックグループであり、これはいくつここに入れていただいても結構だと思います。そのような社会に対して、君主、国家の側はどのように把握しているのかというときに、軍人集団、これもマムルーク朝のようにマムルーク軍人が優越な場合もありますし、東方イスラーム世界のように遊牧軍人が台頭している場合もあります。ただいずれも彼らは、エーリアンである。要するに外から来た特殊な集団を形成するというのが、中世イスラーム史のベースになっている構造であります。そして彼らはエーリアンであるがゆえに、支配階級として統治するためには、イスラームの法や宗教の担い手であるウラマーとのと協力関係をつくっていく。ですから社会を構成する人間が、支配階層であれ、非支配階層であれ、いずれもグルーピングされたものと考えられている。しかも場合によっては、排他的なグループを形成しているように理解されているのではないか。これが第一の問題点であります。
第二点は、すでに触れたことでもあるのですが、統治者がどのような形で社会を把握するのかというときに、統治者は、イスラーム国家を標榜する限り、イスラーム法はもとより、イスラームのさまざまな価値基準というのを実践しなければいけない。それは例えば農民を保護するということであり、あるいはジハード(聖戦)を行うことであり、そのようなことを通じてイスラームの公正な統治者になっていく。そして実際面では、先ほどいった軍人とウラマーの協力を求めていく、という説明ではないのかと思います。では、その説明のどこがまずいと私は考えるのかというと、まず第一に、国家と社会というのでしょうか、あるいは支配者と非支配者というのでしょうか、これが分離されたものとして最初から想定されている。これが第二の問題点であります。
第三点として、その両者が分離されながら、イスラームという共通の規範というものを共有していると想定され、その中で異なる役割を演じている。君主は公正な統治者という役割を演じ、軍人はイスラームの防衛者を演じ、ウラマーはその法的な守り手を演じる、というような具合であります。
以上のような極めてスタティックなフレームに則って説明されながら、そこでは変化は、どのように説明されるのかといいますと、いまいったような要素が一致している場合には王朝や社会は繁栄し、利害が分裂したときに衰退するというのです。しばしば、名君の例として挙げられるサラディン(Salah al-Din 1138-93)やバイバルス(Baybars 1223-77)などは、ジハードを掲げて十字軍やモンゴル軍に対するイスラーム国家の防衛を果たし、内政においても、雑税を廃止し、農民を保護し、宗教施設を建設した。これに対して、15世紀以降は、支配階級が権力と利権の争いに明け暮れ、国家と臣民の利益を省みなかったと歴史家マクリージー(al-Maqrizi 1364頃-1442)は批判するわけです。
これはちょっと最初に申し上げるのを忘れたのですが、いったい誰の議論なのかと思われるかもしれませんが、文献のところについ最近、フランスとドイツでイスラーム、あるいはアラブの通史が、その世界ではリーダーであるGarcinとかHaarmannという学者によって編纂されています(15番、16番)。また、私たちの研究リーダーである佐藤次高さんの最近書かれた通史(『イスラーム世界の興隆』)を見ていくと、十把一絡げというとそれぞれの方に申し訳ないのでありますけれども、あまり意識されていないにしても伝統的にこのようなフレームがあるのではないのか。その問題というのはスタティックな構造に基づきながら、実は変化を説明してしまうというところにあるのではないかと思われます。
5)見直しの方向
では、おまえは、いったいどのようにすればいいというのか。私の見直しの方向というのを申し上げたいと思います。先ず一般論として、いままでの議論の延長線に実はあるのですが、比較の方法ということをかなり意図的に使っていく必要があるのではないのか。図表4が、私のイメージをお伝えするために用意したものです。例えばイスラーム的な要素を考える場合にも、これはすでにいろいろな方がなさっているが、非常に規範的なものとともに、それぞれの地域の中でのvariantを含める必要がある。そしていずれにしても、イスラームの側から説明するのではなくて、その他の諸条件というものを加味したうえで地域を考える。
その上で、先ほどのXYの議論でいいますと、あるYという現象があった場合に、やはりABCD、いくつかの地域の中で比較をして、Xがはたして、共通に原因となっているのかどうかということを、検証していくという作業を意図的に、意識的にやっていく必要があるのではないのか。あるいは非イスラーム世界といわれるような地域での類似の現象はないかということまで視野に入れて議論していく必要がある。これが一つであります。
そして、特にその場合に注意したことは、とにかくイスラームではこのようになっているという形の論法がうまくないのではないか。それはある意味でオリエンタリズムといわれて批判されたものと同じものではないのか。要するにオリエントとはこうであるといっていることと、いかに歴史の資料に基づこうとムスリムの書いたテキストではこのようになっていますということで説明を済ますとすれば、やはり同じような問題を引き起こすのではないのかということであります。このような説明方法を私は「イスラーム中心主義」という言葉で呼んでおります。
それからもう一つは、最近のいわゆる「イスラーム復興運動」という議論を聞きながら思うことは、イスラームの国家というのはシャリーア(sharia)が施行されている国家だ、現代でもシャリーアを施行すべきだというような議論があります。ところが中世史の人間からすれば、シャリーアが完全に施行された国家というのは歴史上には実在しなかったのではないのか、というふうにすら思うわけでありまして、規範的なものや理念だけで議論することの危険は、現代の理解にも関わってくると考えています。
それから2番目は、先ほどの3組、6個の要素の接点にある領域を、意図的に開拓していくことであろう。それは図表の5に書きましたけれども、この要素をそれぞれ別々につなぎ合わせるのではなくて、まさに交点を問題にすべきだろう。そして交点にあるものは何かといえば、それは先ほどいったような行動パターン、behaviorであり、運動であり、あるいはある状況であり、そのようなまさに接点となる部分を、意図的に研究にとりあげていく必要があるのではないのかと考えるわけであります。そして現在、実はさまざまな見直しがすでになされていると思いますが、これについては省略させていただきたいと思います。
そして、それと同時にシステムとしてのイスラームというものについてもさまざまな形で見直しがなされている。これは先ほどIslamicという要素のねじれのことを問題にいたしましたので、改めて申し上げれば、例えばIslamicというのは、非常にmetaphysicalだという理解をされている。ところがコメンテーターでいらっしゃる加藤博さんなどの議論を読んでいると、それを「Islamic」と加藤さんは呼ばれるかどうかはわからないのですが、経済的なシステムを見て、非常に市場的な原理が貫かれている。それはワクフ(waqf)という宗教的な寄進システムについても見られる。その意味で、イスラームを、逆にphysicalなシステムとして見る見方が考えられる。あるいはイスラーム法、あるいは宗教としてのイスラームは、非常に個人主義的である。これは後藤明さんの持論でありますし、法学の柳橋さんも指摘されていることでもあります。その意味ではstructuralではなくて、individualであるということもできる。あるいはglobalとregionalという問題でいえば、まさに多様な地域社会像が提起されている。
そしてその中では先ほどいったマムルークとウラマーというものを別の集団として分けて考えるような見方ではなくて、共通の文化をもつものとして考えていくアプローチの仕方であるとか(M.Chamberlainなど)、スーフィー(sufi)というものを単なる宗教者ということではなくて、むしろ社会統合の装置として考える見方であるとか(私市正年さんなど)、その意味でregionalな社会の仕組みを取り上げながら、先ほどのモザイク的な社会像というものが再検討されているのではないか。
そして最後に、ではどのようにすればいいのかということですが、レジュメに「バーゲニング 個人が状況に応じて取引きし、システムも価値観もカードにすぎない」と書きましたのは、全体的なシステムとしてのイスラームというものも、個々人の価値観も、いずれも絶対的なカードではないということであります。個々の状況の中でいろいろな社会集団が組まれ、政治体制がとられている。そういう意味で常にコンテキストや状況を理解することが極めて重要であって、きょうの私の問題提起では、人文学は社会科学の方法を取り入れるべきだということが基調にあるわけですが、それは普遍的なモデルとか、イスラーム社会の一般的なモデルをつくるためではなくて、個々の運動movementsや現象を取り上げるときに、そのような手法を活用していくという意味であります。つまり、これまでの議論を踏まえたうえで、個別の研究を進めていくということが二つの領域の結婚につながっていくのではないのか、地域研究とはそのような「場」として設定されるべきであろうし、そこに意義があると考えております。
司会 たいへん盛りだくさんの話をまとめていただいてありがとうございました。せっかくのレジュメの中で、いくつか省かれたところもあり、そこにもなかなか面白いことがたくさんありそうなので、そのへんはあとでまた討論の時に、ぜひ伺いたいと思います。いま三浦さんが社会科学への熱い期待が語られましたので、次に長沢さんに、今度は社会科学の側からの提言をお願いしたいと思います。どうぞ。
長沢 ご紹介いただきました長沢と申します。レジュメには「社会科学の側から」としてありますが、実は最初は「近現代史の側から」という話もあったのですが、三浦さんとのお約束で、「社会科学の側から」という副題を付けるということになりました。三浦さんの精力的なお話をうかがって、私は報告ではなくて、コメンテーターに廻った方がいいのではないかと思いました。とくに「社会科学の側から」というタイトルを付けた割には、三浦さんのような理詰めの方法論的な議論ができないように思います。できるとしましたら、方法論的な態度、一種の心構えのようなもので、それを、精神論にならない程度でお話ししたいと思います。
先週一橋大学で、「アジアの長期経済統計」プロジェクトの報告会がありまして、私もやはり2番目の報告をやらされたんですが、その1番目の人がやはり非常に精力的な報告をされて、2番目は非常にやり難かった(一同笑い)。今回も同じようで、レジュメも1枚しか用意していませんし、簡単にお話ししたいと思います。でも、せっかくこのような報告の機会をいただいたわけであり、これまでの拙い研究者としての自己形成の過程、それを振り返るチャンスと考えたいと思います。報告の内容としましては、以前まとめたもの(注:長沢栄治編『中東 政治・社会』<地域研究シリーズ10>アジア経済研究所1991年)の続きのような形になります。
ですからお話しするとしたら心構えというようなもので、具体的な方法論をめぐって、三浦さんのような形でさまざまな諸理論の中に立ち入って議論を尽くすということは、私にはできませんし、一般的な方法論の提案というよりも私が個人的に考えている地域研究の理想像のようなものを語るということになると思います。
私は経済学部の出身ですが、学部時代に、隣の文学部の東洋史の先生のゼミに通ったことがありました。ちょうど当時『岩波講座世界歴史』が出ていまして、その先生はその中で歴史学の方法論を書いていたのですが、その先生がゼミにやって来た私に、「君、こういう方法論なんていうのは、年をとってからやるもので、晩年の仕事だ。若い人がやるもんじゃないんだよ」と言われたことを思い出します。私も、そういう意味では、このようなところで話すのは忸怩たるものがあるのですが、でもときどきこのようなことは議論しなくてはいけないと思いますので、考えるところを少し述べさせていただきたいと思います。
レジュメに書きました「はじめに」というところで、私は地域研究にほぼ20年間携わってきましたが、この20年間で地域研究に対する評価が高まり、社会的な認知が確立してきた、非常に注目されてきたということがいえると思います。もちろん地域研究という言葉自体は、それ以前、戦後直後ぐらいから日本では使われてきたわけですし、地域研究的な営みはもちろんそれ以前からあったわけですが、特に最近そういう地域研究に対する期待が高まり、また地域研究者と名乗っても、それほど変に思われないような雰囲気になってきたのではないのかと思います。
その背景としては、もちろん一番目に、先週の一橋大学の会議で私の前に報告された方のような、またここにも何人もいらっしゃいますが、そのような地を這うような地道な実証研究や資料研究を積み重ねられてきた先輩の方々の努力があります。その一方で非常に迫力のある地域研究論の主張、あるいは地域学というのでしょうか、そうした理論を展開された一種の地域研究のイデオローグ的な先駆者の努力があったと思います。そしてそうした地域研究の成果がこの20年間日本で蓄積された背景には、日本の高度成長期に行なわれたさまざまな社会経済的な条件の整備というものがあったということもあらためて指摘するまでもないことかと思います。
第二の背景は、より直接な時代的な背景といいましょうか、歴史的な背景です。それは、いわゆる言い古された言葉ですが「冷戦体制の崩壊」ということで新しい世界史的状況の中であらためて日本にとっての地域研究は何か、世界の諸地域に対してどのようなものの見方をしていったらいいのか、どのような研究をしていったらいいのかということが問われるようになったということがあります。そのような時代的な状況が2番目にあると思います。
とくに平たく言うと、「国際貢献」に関する議論が冷戦体制後、またとくに湾岸戦争前後に、声高にいわれてきました。こうした状況が地域研究に対する注目あるいは、社会的認知に大きな影響を与えたように思います。そして、このような国際情勢の変化、あるいは世界史的な歴史条件の変化は、同時に世界規模での歴史認識の変化を伴っています。たとえば三浦さんが先ほど紹介されていましたように、現在、人文社会科学におけるさまざまな新しい方法論をめぐる議論が行なわれ、一種のパラダイムシフトが問題とされ、また「歴史の読み直し」の作業が進みつつあるのは、まさにこのような大きな現在の状況と結びついていると思います。
そういうわけで、レジュメでは「伝統的な地域研究」と書きましたが、これは60年代、70年代ぐらいに通用した研究でして、かつて林武さんが紹介されたアメリカからの地域研究の流れを引き、日本的な形で発展したものです。しかしこの60年代、70年代の地域研究が現在、新しい状況の変化の中で変わりつつあるような気がします。
この伝統的な地域研究は、レジュメで括弧の中に書きましたように、政策科学、政策研究として出発したという点と、それと結びついていますが、一国単位で研究が行なわれたという特徴があります。そのような古いタイプの地域研究から現在新しいタイプの地域研究への変化が求められています。そこでは地域概念そのものを問い直すさまざまな試みがなされています。狭い意味での地域研究からもっと開かれた広い意味での地域研究へと変わってきた。簡単に言ってしまえば、国民国家の枠を超えた地域の問題であるとか、またその下にある地域の問題であるとか、そのような重層的な地域、「地域概念の重層性」ということを強調する議論がますます行なわれるようになってきます。もちろんこのような議論は昔からあるわけで、板垣(雄三)先生の本などには見られるように昔からあるわけですが、最近さらにそのような見方が再認識されるようになってきた。今回の「イスラーム地域研究」プロジェクトがということで文部省の支援を得ているというのは、恐らくそのような背景もあるのではないのかと思います。
この新しい地域研究の中身についてはあとで触れることができるかもわかりませんが、例えばレジュメの中に書いてありますように、「地域概念の再検討」というところで環境論ですとか、括弧付きでありますが「文明」論の台頭というか、復権というようなものが見られるようになったような気がします。その他にも、さまざまな、先ほど三浦さんがおっしゃったような方法論的な展開ですとか、フェミニズム研究に対する関心の高まりですとか、さまざまなそのような新しい研究の潮流の中で、この地域研究の見直しと新しい展開が見られると思います。例えばまず第一にレジュメでは「環境論」と書きましたが、地域研究と自然科学の関係を見直す議論があります。すなわち、自然環境などの問題に取り組み、自然科学的な研究との交流を深める形での新しい総合的な地域研究の試みがなされていると思います。これはかつて流行した風土論的な研究とは大きく異なるものであります。
また次に「文明論」とレジュメでは括弧付きで書きましたが、私は実は文明論というのがよくわからないものでありますから、括弧付きで書いたわけですが、冷戦後の現在の状況において、さまざまな古い形の文明が、欧米的な近代西欧文明に対抗して自らの普遍性を主張し、一種のグローバル化をしているような現象が見られるという議論もあります。後者の点については、三浦さんも言っていますが、私も事あるごとにしつこいぐらい言っていますし、ここにいらっしゃる皆さんは耳にタコができるぐらい聞いていると思いますが、いわゆる本質主義、還元主義的な議論というものにはくれぐれも警戒しなくてはいけないと思うわけです。いずれにしてもこのような新しい地域研究の広がりを求める声が出てきております。
一方、前者の「環境論」について、自然科学と地域研究との接合との問題について述べてみますと、中東の場合は、水をめぐる問題が大きいわけです。しかし、その場合でもいわゆる環境決定論的なものには非常に警戒をしなくてはいけないと思います。ガマール・ヒムダーンは、そのような環境決定論的な考え方、いわゆる東洋専制国家論的な考え方と格闘をしたエジプトの地理学者でありますが、その議論を通じて、地域概念を広げる、地域を重層的に捉えるといったきを問題提起をしていることを一応指摘したいと思います(注:長沢栄治「エジプトの中央集権性─ガマール・ヒムダーン著『エジプトの個性をめぐって』─」後藤晃・鈴木均編『中東における中央権力と地域性─イランとエジプト』アジア経済研究所1997年)。
しかしながら、ここでしかしながらというところなんですが、私は非常に保守的な人間でありまして、私自身にとっての地域研究というのは基本的には社会科学の研究だと考えております。ときどきほかの世界も取り入れたいと思いますが、自分自身は社会科学の中をソロリと歩くことで精一杯だと考えております。またもう一つ指摘したいのは、私が考える地域研究はあくまでも現代研究だということです。ここでいう現代研究とは、現代だけのことを研究するという意味ではなくて、現代を理解するための研究という意味でありまして、限定付きですが、そのような古典的な、保守的な立場からでありますが、ここで地域研究について私は考えていることをちょっと述べさせていただきたいと思います。
以前からちょっと地域研究を論じたときに、ちょっと申し述べましたけれども、だいたい地域研究論を議論する場合に、だいたい二つの大きな問題のトピックがあるように思います。一つは政策との関係というか、もしくは国家の政策はその一部でありますが、社会に対する研究成果の還元という問題があります。その場合、地域研究の社会還元というのは、まさに研究の持つ政治性をめぐる問題です。もう一つは、仲間内の議論でありますが、いわゆる専門科学との関係の問題であり、地域研究の学問的なアイデンティティーはいったいどこにあるのかというテーマです。今日は、後者のほうに少し中心を置くというか、後者についてのみ言及することになると思います。
以下レジュメを中心にとくに「社会科学の地域性とか民族性」といった問題を中心に議論したいと思います。では、冊子のほうのレジュメを読み上げながら解説する形で少しお話ししたいと思います。まずこの地域研究の問題というのは、ここでは先ほど上げた二つの一つでありますが、地域研究と専門科学との関係に限って見ても、なかなか難しい問題であります。私はときどき考えるのでありますが、地域研究者は専門科学に対する研究の素材を地面を這いつくばったりなかなか手に入らない資料を加工して、そのような面白い研究素材を理論研究を得意とする人に対して、提供すればいいのだと達観すれば、それはそれで非常に気楽なことです。しかし、そうではなくてやはり「出身科学」と書きましたが、自分が一応専門としている専門科学に何らかの貢献をしようと、恩返しをする、フィードバックをする義務があると考えると非常にまたこれは難しい問題だと思います。
その場合、特に確立した専門科学の特定の何とか学派とか、何とか理論などの看板を背負いながら地域に研究に入った場合は、なかなか非常に気苦労も多いですね。苦労されている方も多いのではないのかと思います。いっそうのこと地域研究では、私は元何とかをやっていましたということのほうが楽ではないかと思うのです。しかしなかなかそのようなことは言えず、私は専門は何々で、地域は何々をやっていますよということになり、なかなか大変ではないかと思います。
私は、大学でいわゆる西欧経済史、大塚史学を勉強しました。大塚史学と言っても、今日ではほとんど死語に等しい(一同笑い)、今さら批判する人もいないのではないのかと思うような具合で、昔ある人に言われたことですが、大塚史学というと、何かアジア的共同体でも発見するつもりでやっているんですかとか、あるいは局地的市場圏がどこかにあると考えているのですかなどという話も聞きました。今頃そういう素朴な議論をする人はいないと思います。しかしながらある程度、あとでも述べますようにそのような日本の社会科学、あるいは人文科学の系譜をそれなりにふまえて研究を行なう姿勢も重要ではないかと思うわけです。というのは、地域研究は単に理論の地域的な適応という応用研究にとどまるものではなくて、むしろそのような理論とか、通説とか、学説などと地域の現実、あるいは現実を解釈する地域的な知のあり方、これは人類学的な言い方でありますが、そのようなものとのズレに何らかの意味をもたらす試みとしても地域研究はあるのではないのかと私は最近考えているからです。
その場合、この次に書きましたのは、日本人の研究者として、日本人の民族性を強調するのは、エスセントリズムでよくないという批判を招くかもしれませんが、日本人が徒手空拳で現地社会にいって文献調査なりをしてやろうと思うときに、自分自身が持つバックグラウンドとか、能力ということを考えてしまいます。その場合、私たちにとってだいたい三つぐらいの方法論的な態度の可能性が考えられるのではないのかということです。これは別に日本人に限ったわけではなくて、欧米人以外の、韓国人でも、中国人もいいのかもしれませんし、これは別にイスラーム地域に限らず、どこについてもいえることなのかもしれませんが、常識的なことですけれども、一つは欧米を中心にした近代の人文社会科学の伝統に立つ態度です。その場合、これまでの理論や通説の流れやまた最先端の動向を踏まえた努力が絶えず必要になります。またときどきそのような専門家の方々が行なう非常に自虐的と思えるような議論、そのような愚痴を聞きながら地域研究を目指すという態度も必要であります。
2番目は、先ほど大塚史学のことをいいましたが、近代の日本で発達した、固有に発達したというと、ちょっとこのへんが議論を呼ぶかもしれませんが、日本の人文科学や社会科学で知的遺産に振り返るということです。それによって資料へのアクセスとか、現地での研究拠点の確立といった点で優位に立つ欧米の研究者や現地の研究者に対して、いわば研究の後進国である日本人の研究者は、一つの知的なツール、あるいはユニークな視点をもつことができるのではないか。この点はぜひ皆様の議論をぜひお聞きしたいところですが、そのような2番目の態度があります。
3番目は対象地域における現地主義といってもいい態度でして、思想的な展開、あるいはそこでの固有の人文社会科学の発展というものをきっちりと踏まえるということです。こうした広い意味での近代的な社会認識の枠組みと欧米での社会科学や人文科学、もしくは近代日本での遺産といったものを、それぞれの比較することに何らかの意味をもたせるということも、比較研究としての地域研究が、取るべき戦略の一つである。私としてはそのようなやり方を個人的にやりたいという意味を語っているわけです。
その背景としては、先ほどちょっと述べましたが、社会科学においても既存の学問体系や社会認識の枠組みに対する批判ですとか、あるいは普遍的な理論に対する批判といったような状況が現在見られるからであります。これは歴史研究の場合、そのようにかつて通用したようなグランドセオリーとか、英雄中心のビックヒストリーなどを見直し、よくいわれることですが、「歴史なき人々」に対する注目ですとか、そのような新しい方法論的な問題提起がなされています。さらにはたまたま私がレジュメを書いた時に、山之内(靖)先生の『マックス・ヴェーバー入門』を読んでいましてこの報告との関係で感銘を受けたのが、近代知としての社会科学に対する批判の言葉です。すなわち、社会科学は新しい中世神学として、その近代的な転位形態となったという点です。近代西欧の社会科学の批判、再構築という作業において、そのような比較の視点に立ちながら、社会認識や文化理解の地域性とか、民族性というものを追求する試みというのは、地域研究の重要な課題の一つとなると考えます。ここで社会科学の民族性と申したのは、私の造語ではなくて、私が前に勤めておりましたアジア経済研究時代の先輩にあたる山口さんが『地域研究論』のなかでそのような社会科学の民族性について述べているところからちょっと借りてみたわけです(注:山口博一『地域研究論』<地域研究シリーズ1>アジア経済研究所1991年)。
この問題について私自身の仕事としては、例えば各地域で展開されている資本主義論争、資本主義の性格規定をめぐって、これは問題としてちょっと古いですけれども、日本をはじめとした各地域で行われた資本主義論争の地域性のような問題で、いわゆる世界システム論やその他の理論と接合する形で考えてみたいと思っておりました。また最近私が取り組んでいるのは、知識人の個人史パーソナル・ヒストリーを通じて、その地域固有の社会認識の歩みが、どのようなものであったのか、もしかそのような社会認識に民族性をめぐる言説がどのように形成されてきたのかということを研究したみたいと夢想しているわけであります。
しかしその場合、私は重要だと思うのですが、このようなことをやっていると、ある意味での完全な相対主義的な立場になってしまう恐れがあります。その場合は、やはり私は古いかもしれませんが、方法論的前提としては、いわゆる西洋近代の問題を考える必要があると思います。山之内先生にいわせると、「西欧近代が持っている合理化の普遍性の恐るべき運命的力」というものですが、そのようなものをやはり前提として考える。言いかえますと、近代というものをどのように扱うのかということが地域研究にとって非常に重要だ。それが私が考える狭い意味での地域研究であると思います。そのような近代がもつ一つの側面として近代社会科学というものを実は考えようと思っております。
あまり詳しく展開するとボロが出ますので、このぐらいに止めますが、その場合にそうした近代への批判をたえず忘れない、その限界性を認識して相対化するということが重要です。
社会科学の認識というのは、ウェーバーの理念型に見られますように相対的なものにすぎないというわけであります。この点はちょっと省略させていただきます。
しかしながら、このような地域研究とか、地域性、それぞれの社会科学なり、社会認識の地域性を追求しようという考え方に対する批判する立場もあるわけです。ここでは同業者で直接誰が批判しているということではなくて、一般的に考えられる批判の立場を示してみたいと思います。それは、いわゆる普遍主義的な立場に立って、特に現代社会をどのように認識するのかという点で、いくつか批判があるのではないのかと考えられます。
例えばここにも人類学者の方が何人かいらっしゃいますが、「人類学者は地域研究者になってはいけない」という話も人類学者の間ではなされているようです。それは「地域屋」にはなってはいけない、悪い意味での地域学者になってはいけないという意味だと思います。しかしながら現代を理解するための地域研究というとき、人類学が深くかかわりをもつ現代思想、例えばポストモダンとかといっているような思想については、私は暗くてよくわかりませんが、そのようなところにいったい地域性はどのような意味を持つのかという問題があります。たまたま最近読んだもので、ちょっと現代文学から引用してしまいますと、安部公房さんが、エッセーの中で「地域性を越えたところに成立する、地域性を否定したところに成立するというのが現代というものである」ということを言っています。さらに「そもそも現代文学というのは、文学としての意味をいうのなら、発展途上国には存在しない」ということも言っているわけです。彼は「発展途上国の多くの地域が植民地的な文化的な収奪の対象になってしまって、そこには読むに足る現代文学が存在しないのだ」ということをおっしゃっている(注:阿部公房『死に急ぐ鯨たち』新潮社1986年)。
これを読んで、では私が比較しようとしているそれぞれの地域の社会科学なども考えてみたら底の浅い比較に足りないものだろうか、とふと思ってしまいましたが、いや、そうでもないだろうという気もするわけです。
もう一人、私は、彼自身が地域研究者としてなかなか注目したらいいのではないのかと思うアメリカ人の小説家、リービ・英雄の本を、これもたまたま最近読んでいましたら、彼は現代文学ということに注目するのですが、世界に「現代」が存在するとしたら、それは10いくつかの都市、それらはニューヨークとか、東京とか、ソウルとかが含まれている、カイロとか、イスタンブールとか、テヘランが、その10いくつに入っているかどうかよくわからないのですが、その10いくつかの都市の中に真の現代があるといっているのです。その西洋と非西洋の移動の中に真の現代があるのであって、移動体験が表現を得たときに真の文学になるといっています(注:リービ・英雄『新宿の万葉集』朝日新聞社1996年)。真の現代文学がそこに成立する。現代というのはいったいどこにあるのか。私は、先ほどいわゆるなぜ地域研究をやるのかというと、現代社会を、私は世界全体を丸ごと把握しようなんて毛ほども考えておりませんが、とにかく現代とは何かということを関心を持って研究をしているわけです。その場合に地域性に関心を集中させるというのはいったいどういう意味があるのかということを、ちょっとこのような現代文学に関係ある人からも問題提起を考えると、そのようなことを突き詰めて、あまり物事を突き詰めて考えないといい場合もありますが、しかしそういう反省をしなくてはいけないところがあるのかという気もいたします。
とはいっても、一つの考え方として地域研究は、既存の知的な社会認識や文化認識の秩序に見られるヘゲモニーというものを揺り動かすというか、回りからちょっと離れたところがそれを突き動かすといったところに意味があるとするならば、それなりに地域研究をやるという意味もあるのではないのか。さまざまなコミュニケーションの手段も発達し、世界の各地機関の交流や交通が拡大するからといって、そのようなヘゲモニーをもつ社会認識や文化認識が均一化していくわけではない。むしろそういった近代社会科学やヨーロッパに成立したといわれる近代的な社会認識というか、社会科学のあり方というものを、それが世界的に展開する中でそれを相対化していく努力というのが地域研究者に与えられた課題ではないのか。ちょっと精神論みたいで恐縮ですが、そのように思います。その場合に、既存の専門領域や研究領域に対して、非常に柔軟な開かれた態度をとるべきことが必要ではないのかということで2番目の問題に移ります。
2番目の問題は、時間のこともありますし、簡単に済ませたいと思います。それは、既存の科学の諸体系に対して、周辺的な存在であるということを自覚している地域研究者は、そのような諸体系に対して、つかず離れずの柔軟で流動的な態度を取ることを試みていいのではないかということです。ちょっといい加減な言い方かなと思いますが、そのような専門領域の塀を飛び越える流動的で開放的な態度が必要ではないのか。「専門科学の番人をするのはシオンの守人」とかと英語でいうのを本で読んだことがありますが、そういうあまり専門的な境界線に目くじらを立てずに流動的で開放的に境界を飛び越えていくことも必要ではないのかと思います。
その場合、現代中東研究の専門分野は、だいたい三つぐらいの類型があるのではないのかと私は思います。一つは国際関係や地域横断的な問題を扱う領域とあります。2番目が本来の地域研究、狭い意味の地域研究が扱った「一国単位のポリティカル・エコノミー」と書きました。ここで限定しすぎかもしれませんが、それを扱う領域です。そして3番目に、それらの下方に広がる文化や社会の領域であります。これは垂直的な区分であります。
これも私が初めて考え出したことではなくて、唯一の中東のポリティカル・エコノミーの教科書といっていいと思いますが、RichardsとWaterburyの本の序文で「中東研究には二つのグレートゲームがあって、一つは域内紛争を中心にした国際政治の領域で、もう一つは開発と国家の問題を扱うポリティカル・エコノミーであるといところから取ったものです(注:Alan Richards and John Waterbury, A Political Economy of the Middle East, Westview Press, Boulder, 1990)。さらに私はもう一つの領域を、さらに下の基層的な社会と文化に関する研究もあるのではないのかということでつけ加えてみたわけであります。
ここで、私が中東研究を始めてから過去20年間ぐらいの日本の研究状況を振り返ってみますと、第1番目の領域ではジャーナリズム出身者を含めて、非常に鋭い現状分析が進められていると思いますし、3番目では人類学者や現代イスラーム研究者が非常に精力的にやって、目覚ましい展開があったように思います。これに対して本来の「伝統的な地域研究」の対象領域である2番目の一国研究ですが、地域研究というのは東南アジアなど他の地域と比べますと、非常に見劣りがするというのは正直な反省であります。とはいっても、実はこのような問題領域の境界線をできるだけ自由に飛び越えていく試みがなされるべきだと思いますし、実際に多くの地域研究者はそれぞれ特定の専門から出発しながら、それは社会の要請とまた個人的な関心のうつろいに従いまして、それぞれの境界を飛び越えていったのではないのかと思います。
それについては中東というのは研究者の数が少なくて、そのためいろいろな注文に私自身も恥ずかしげなくいろいろなことを書いてきたという反省もありますが、しかし、それは逆のメリットもあるのではないのかという開き直りたい気もします。積極的にいいますと、むしろ中東的な特徴として、研究対象そのものが非常に流動的な問題、イスラーム運動の国際性ですとか、対象そのものが境界線を越えて動いていると考えているわけで、そのように考えますと、ちょっと初めにも述べました地域の重層性といったものと研究領域の重層性がある程度対応し、重なり合う運動ではないのかと思います。
ここで、結びに入りますが、以上私はほとんどイスラームの「イ」の字もいわないで話を進めてきました。というのは私自身はイスラーム研究者ではないと思っていますし、前の「イスラームの都市性」プロジェクトでもメンバーでなかったですし、しかし今回なぜ入っているのかというと、それは職場の関係かなと思っております。この学会も、実は昨年入ったばかりで、現在の勤め先の英語の名前がオリエントですから、同僚、先輩の方々が封筒書きしたりして努力されているのをみて、やはり学会に入らなければと思って入った次第です。それはともかく、私は、ですからイスラーム研究者ではなくて外部から見ている者の見方として、ここで申し上げているわけですが、ここでいままで申し上げた地域研究の夢というのは、私自身の個人的な研究の理想像のようなものであります。
もう一つの夢というのは、きょうは研究代表者がいないので、このようなことをいってしまうのですが、地域研究というのは一時の儚い夢であるという可能性もなきにしもあらずということです(一同笑い)。いまイスラームとか、地域研究というのが注目されていますが、10年ぐらい、20年ぐらいたつと、「何をやっていたのか」という時代が来ないとも限らない。そのぐらいに発展的解消、日本のイスラーム理解、もしくは地域研究なんて今さらやらなくてもというぐらいに、この日本の研究状況なり、社会的な、社会全体の広い意味での知的な蓄積があればいいと思うのですが、そうではなくて、まったく儚い夢に終わるという可能性もあるかもしれないと、タイトルを付けたあとでそのように思いました。
ここで、少しは三浦さんとの報告との引っかかりを付けないといけないので、一言だけ、disciplineとしての専門領域としてのイスラーム学やイスラーム史ということについて述べたいと思います。私はよくわかりませんので、これは両者がどのように結びついているのか、その中をどのように区分できるのかよくわかりませんので、あまり詳しい分類をするのは避けたいと思いますが、しかし外から見ていると、これは一つの専門領域です。これは文字どおりdisciplineですから、特定の時間、期間をかけて、ある場合にはテキストに従って体系的に勉強すべき領域があり、また実際にそれを追求されてきた方々が、日本のイスラーム学、イスラーム史の中心になっていると思います。
私はその外にいるわけであります。しかし、この専門領域にもやはり先ほど述べました社会科学などについてと同様のイスラーム研究の地域性とか、民族性とか、そのようにいってしまうとちょっと言葉がきついですが、日本における研究の独自性といったようなものがやはりあるのではないのかと思います。そのようなものを自覚的に明らかにするということもやはりイスラーム地域研究ということになる以上、重要になってくるのではないのか。対象とする地域や時代、また専門領域を越えて研究者が交流することに意味があると考えております。私はGibbが言っている「結婚」という古典的なテーゼも、無理に結婚すればいいというものではないと思います。でも、全然そっぽ向いてもしょうがないので、私もそういうイスラーム地域研究の中で、これから交流して、私はこれから体系的にイスラーム史とか、イスラーム学をこれからやるつもりはないだろうし、できないだろうと思いますが、少しはそのようなことにも積極的な発言ができるように勉強してきたいと考えております。以上であります。
司会 どうもありがとうございました。社会科学の側から長沢さんにいろいろな提言をいただきました。しかし話の中にはかなり人文科学的な要素も入っていたと思います。
司会 コメンテーターの方に順次、お願いしたいと思います。まず最初にモジュタバ・サドリアさんから、その国際関係論の見地からお願いしたいと思います。サドリアさんは、英語でお願い出来るそうです。お願いします。
サドリア(近々掲載予定)
司会 Thank you so mach, very constructive remarks. では、その次に今度は加藤さんにお願いします。
加藤 非常に高い日本の中東学界への評価を与えられた後に、とんでもなくレベルの低いコメントになるかもしれません。
二つの基調講演は、一方では歴史学、他方では社会科学の側から、「地域研究」のあり方を問うという内容のものでした。そこで、私のコメントも「歴史学」「社会科学」「地域研究」の三つをキ−ワ−ドとして話そうと思います。
とはいえ、その内容は、二つの基調講演のように、「歴史学」と「社会科学」の立場から「地域研究」のあり方を問うという正攻法のスタイルをとらず、「地域研究」と「歴史学」、あるいはより正確には「歴史研究」、という二つの研究分野が基本的には同質のものであるということを指摘するなかで、私なりの「地域研究」観を述べるというゲリラ戦法をとろうと思います。
というのも、私には、「地域研究」と「歴史研究」には、次の二点において共通性があると考えるからであります。
第一は、「歴史研究」がディシプリンあるいはセオリ−に対して妙なコンプレックスをもっていることはよく指摘されるところですが、どうも「地域研究」もまた、このコンプレックスに悩んでいるらしいということです。つまり、自分たちの研究の評価をディシプリンあるいはセオリ−との関係からしたがり、自分たちの研究がグランド・セオリ−のなかに位置づけられ得るか、あるいは既成の専門分野と並んで、一つの専門分野として認知され得るのかということに、大変なこだわりをもっている。
第二は、「歴史研究」の評価はその作品としての質の高さによるとはしばしば聞かれるところですが、どうも「地域研究」論を精力的に展開している京都大学東南アジア研究センタ−の立本成文氏などの議論をみてみると、「地域研究」もまた、結局のところ、研究者の斬新な着想に基づく研究材料の処理という、職人芸的な個々の「作品」としてのできばえの高さによって評価されざるをえないらしいということです。これは、ある意味では、「地域研究」は一つのディシプリンではないという考え方を言い換えたものにほかなりません。
以下、この「歴史研究」と「地域研究」との間の類似性という第二の点に関して、私の「歴史研究」観を述べるなかで少し敷衍してみたいと思います。
まず最初に述べておくべきは、私自身は「歴史学」あるいは「歴史研究」を一つの独立したディシプリンとは考えていないということです。本日、この場に、カリフォルニア大学教授で北米中東学会の機関誌編集長であるステファン・ハンフリ−ズ氏がおられますが、その彼が先日のアメリカ合衆国でのイスラム史研究を回顧した講演を、歴史学はディシプリンではないという言葉から開始されましたが、私はこのハンフリ−ズ氏の立場に同意する者です。
とはいえ、正直なところ、現在の私は「歴史学」あるいは「歴史研究」がどういう学問であるか、あるいはどういう学問であらねばなかないかについて、思いをめぐらすことはほとんどありません。もっとも、このような私でも、知的に誠実な時代はあり、若い頃には、人並みに「歴史学」とディシプリン、あるいは「歴史研究」と「社会科学」との関係はいかにあるべきかと思いを巡らしたものです。
しかし、もう15年も前になりますが、ポ−ル・ヴェ−ヌという、フランスのアナ−ル学派と深い関係をもちながら研究をすすめているヨ−ロッパ古代史家の歴史学の方法論をめぐる議論に出会ってから、こうした「歴史研究」の方法論について思い悩むことをやめました。
そこで、ポ−ル・ヴェ−ヌの議論ですが、彼の歴史学の方法論をめぐる著作については、三点─(1)『歴史をどう書くか』(1982年)(2)『差異の目録 新しい歴史のために』(1983年)(3)『ギリシア人は神話を信じたか』(1985年)─が法政大学出版局によって翻訳されています。そのほか、フェルナン・ブロ−デル関係の論文集には、かならず彼の論文やエッセイが収められています。
そこで、ポ−ル・ヴェ−ヌは歴史学の方法論を、とりわけ歴史学と社会科学との関係について、さまざまな角度から論じていますが、私の目に止まったのは、彼の天文学との比喩によって歴史学を説明する叙述でした。それは大略、次のような内容のものでした。
人文・社会科学の歴史学はたとえて言えば、自然科学の天文学のようなものだ。宇宙の現象を説明するのに天文学的な説明というものはないだろう。あるのは物理学的、数学的、統計学的説明である。しかし、だからといって、宇宙が存在し続けるかぎり、天文学という学問がなくなるわけではない。
同じように、人間社会の現象を説明するのに歴史学的な説明というものはない。あるのは、社会学的、経済学的、政治学的、等々の社会科学的説明である。しかし、だからといって、この地球が破滅せず、人間社会が存在し、世代交代を続けるかぎり、歴史学という学問がなくなることはないであろう。
と言うわけで、このような内容の議論に出会ったからは、私は、歴史叙述をどのように工夫するかに思いをいたすことはあれ、歴史学の方法論に思いを巡らすことはほとんどなくなったのです。
ところが、今回、フォ−ラムでのコメンテ−タ−の役を依頼されました。依頼された時、ただちに私の頭に浮かんだのは、このポ−ル・ヴェ−ヌの議論でした。そこで、15年振りに、改めてかつて読んだポ−ル・ヴェ−ヌの著作を手に取り、先に指摘した内容の文章がどこにあったかを確認することにしました。そして、次のような二つの文章をみつけることができました。第一は、
「歴史は本当にあった出来事の物語(レシ)である。この定義の枠内で考えると、歴史の権威を手にするには、ひとつの事実がたったひとつの条件をみたしていればよいことになる。つまり、現実に起こった、という条件をみたしていればよいのである。」(『歴史をどう書くか』22ペ−ジ)
という文章です。この文章は、私にはミシェル・フ−コ−やエドワ−ド・サイ−ド流のディスク−ル分析、文化分析の行き過ぎをいさめる内容になっていると思います。というのも、彼らの分析には、ともすれば「事実は現実に起こった」ということさえ踏まえぬ、言葉と概念の遊戯におちいる危険性があるからです。
この点についても、ハンフリ−ズ氏は、先日の講演のなかで、行き過ぎたオリエンタリズム批判という形で指摘されております。私は氏の指摘に共感をもつ者です。次いで第二は、
「歴史だけに特有な歴史的な説明というものは存在しません。ほかの多くの学問と同様に、歴史は別の科学すなわち社会学に助けを求めながら、自分の素材に形式を与えます。同じことで、数多くの天文学的現象がありますが、私の誤解でなければ、天文学的な説明というものは存在しません。すなわち、天文学事象の説明は物理的なものなのです。にもかかわらず、天文学講義は物理学講義ではありません。」(『差異の目録』4-5 ペ−ジ)
という文章です。ポ−ル・ヴェ−ヌはフランスの学者ですから、ここでの社会学は、アメリカの学界におけるがごとき狭い意味の社会学ではなくて、経済学や政治学なども含む、社会の学問という非常に広い意味をもって使われています。
この文章こそ、天文学との比喩によって歴史学を説明する叙述です。その内容から判断するかぎり、私の先の要約は間違っていなかったわけで、私もまだ耄碌していないわいと、一人悦に入ったのですが、ポ−ル・ヴェ−ヌの著作のペ−ジをめくっていて、歴史学と天文学の比喩とは別の、もうひとつの面白い比喩的な比較が目に止まりました。
それは、歴史学と社会学との比較を試みるなかでポ−ル・ヴェ−ヌが試みた表現であり、歴史学を「対象のある学問」、社会学を「対象のない学問」と呼んでいることです。ここで歴史学の対象とは現実に起こった出来事を指しますが、社会学には対象がないという表現をもって、文字通り社会学には対象がないと理解してはなりません。
ポ−ル・ヴェ−ヌの議論はポレミックで修辞に満ちたものですが、ここでも、対象がないとは、あくまでも比喩的な表現であって、ポ−ル・ヴェ−ヌが言わんとしていることは、社会学という学問が、具象的、具体的な現実ではなく、社会類型、社会システムなど、具象的、具体的な状況を捨象した、普遍的で抽象的な概念を研究の対象にするということなのです。つまり、この比喩は、先の天文学との比喩によって歴史学を説明する議論の延長線上に展開されているのです。
ところで、これは時間についての学問である歴史学についての議論ですが、「対象のある学問」、「対象のない学問」という議論を、空間についての学問に適用してみると、どういうことになるでしょうか。つまり、ポ−ル・ヴェ−ヌは歴史学の具体的な研究対象は「出来事」だといっているわけですが、空間の学問において彼がいうところの具体的な研究対象とは何であろうかというわけです。
それは、私のみるところ「地域」であります。そして、この具体的な対象たる「地域」を扱う学問こそ「地域研究」にほかなりません。いや、空間の学問として、まず挙げるべきは地理学であるという反論があるかもしれません。
しかし、私が理解するかぎり、地理学は景観類型や空間システムなど、普遍的で抽象的な概念を研究の対象にすることが多く、時間の学問における対象のない学問、つまり社会学に相当するものと考えられます。つまり、歴史研究に対して社会学があるように、地域研究に対して地理学があるというわけです。
私がこのコメントの冒頭で、「地域研究」と「歴史学」あるいは「歴史研究」の二つの研究分野は同質なものと考えられると述べたのは、この意味においてであったのです。「歴史研究」において「出来事」と「時間」は区別されねばなりません。同様に、「地域研究」において「地域」と「空間」は区別されねばなりません。
「時間」と「空間」が抽象的で物理学的な概念であるのに対して、「出来事」と「地域」は具体的でひとによって生きられている現実です。「歴史研究」が生きた「出来事」を、「地域研究」が生きた「地域」を研究対象とするという点において、両者の学問の質は同じです。ただ縦のものを横にしただけです。
周知のように、フランスのアナ−ル学派は「歴史学」と「地理学」、つまりは「時間の学問」と「空間の学問」の結婚をうたい文句に出発いたしました。アナ−ル学派の創設者たち、マルク・ブロック、ルシアン・フェ−ブルの時代の地理学、たとえば、具体的な景観の叙述の列挙からなるヴィダル・ドゥ・ラ・ブラ−シュの地理学は歴史学と結婚できたかもしれません。
しかし、現在の地理学は具体的景観叙述のレべルをはるかに越えて、抽象度の高い研究対象をもつ学問になっています。したがって、現在の研究状況で幸せな結婚となる可能性の高いカップルは、歴史学と地理学ではなく、歴史研究と地域研究ではないかと思われます。
ものの考え方の違う者同士、育ちの違う者同士、身分の違う者同士の結婚は、往々にして破綻するものです。高い理想を諦め、パタ−ン化した、究極の恋愛におぼれることなく、具体的な現実のなかに身分相応の喜びを見いだそうとの姿勢において共通する歴史研究と地域研究は、お似合いのカップルになるかもしれません。
しかし、そのためには、歴史研究と地域研究は、おたがいに自由な考え方、行動を認め合わなければならないでしょう。具体的には、おたがいに、説明、叙述のための道具、つまり社会諸科学を自由に使うことを認め合う、懐の広さがなくてはなりません。「歴史研究」と「地域研究」においては、研究対象をそのリアリティのなかで、具体的に把握できてさえいれば、方法論的にはオポチュニストでよい、というのが私の考えです。
もっとも、現代では結婚が唯一の幸福なカップルの結合形態ではなく、またカップルもかならずしも男と女である必要はないようですから、結婚以上に刺激的でスリリングな結合関係が可能かもしれません。しかし、私のように想像力が貧困で、生命力のボルテ−ジの低い者には、常識的な結婚でさえ手に余ります。
司会 どうもありがとうございました。だんだん、皆さんの結婚の比喩以来、恋愛論まで広がってまいりました。大変その議論がこれから先楽しみでありますけれども、3番目に今度は言語学のディシプリンから、しかも現実には実にいろいろなユーラシアの各地に飛んでフィールドワークを展開されている林徹さんからコメントをいただきたいと思います。
林 林です。どうもありがとうございます。結婚の比喩がずうっと続いているのですが、言語学というのはいままで結婚相手としてはまったく登場しておりませんで(一同笑い)、私としてはもっぱら地域研究に対して片思いを続けているというような状況です。
皆さんの議論をお聞きしておりまして、もうすでに四つのテーマが出ております。3題話どころか、4題話を組まなければいけないという、これはとてもとても難しい話になってきました。そこで、これはこのようなパネルの常套手段ですが、自分の予め多少用意してきた話題に引き付けて、皆さんのお話とつじつまを合わせるということをやらざるを得ません。いままでのお話を伺っていますと、ちょっと地域研究ということから外れるかもしれませんが、フィールドワークという、(私自身は非常に限定的なフィールドワークしか行っておりません。この会場にはもっともっと百戦錬磨のフィールドワーカーの方たちがいらっしゃいます。)そのフィールドワークを多少とも研究の中に取り込んで生活を送ってきた者として、いままでの議論を考えてみたいと思います。
一応言葉のことをやっておりますので、言葉の研究を例にとりますと、フィールド言語学、つまりフィールドワークを行う言語研究者のグループが、しっかりした集合ではなく、非常にファジーな形であるにしろ、考えられます。そういう人たちは何をやってきたのかというと、実際に現地に赴いていろいろな言語を記述し、それを持ち帰って分析するということを続けてきたわけです。この分野は、先ほど三浦さんがお話になり、ある意味では長沢さんもおっしゃっていた、確立した既成の知の体系に対する挑戦というか、それを揺るがすものとして発展してきた部分があります。
というのも1960年代、あるいは50年代の後半から北米を中心にしまして、言語学の非常に有力な理論が展開していきます。ただこの理論は、主に英語という言語を対象にして理論化を進めてきたためにいろいろな欠陥を抱えていました。そして、多くの問題点が、フィールドでさまざまな言語を研究してきたフィールド言語学者により指摘されました。つまり、確立された理論に対する外からの揺さぶりという形で、フィールド言語学が発展してきたとも言えると思います。
ところが、単に既成の体系、あるいは既成の理論に対するアンチ・テーゼということだけではやはり、長沢さんのお話にあったように、そこに安住してしまえば非常に楽なのですが、フィールド言語学者としては満足できない。そこで、自分たちは多様性の単なるコレクションを目指すのではないという理論化を行う羽目になります。三浦さんのお話の中にあった、まさにGibbの批判に当たるわけですが、それに呼応するような形で70年代だと思いますが、linguistic typologyという分野が活性化し、言語における普遍性に関する議論が起こってきます。つまり、さまざまなバラエティーを集める、収集することによって、人類が持つ可能な言語の範囲というものを考えていく、それが言語の普遍性を反映している、という形でまとめていこうというわけですが、一方では、個別の言語の記述、あるいは個別の言語のコレクションということを、どこかで合理化する意味もあったのではないのかと思います。
さまざまな普遍的言語特徴が提案されてきます。当初は例えば言語の語順に関する普遍性が提案されました。しかし、さまざまな言語の収集が進むにつれて、普遍的特徴を相対化せざるを得なくなってきた。当初の少ないデータの範囲で普遍的に人類の言語に備わっている特性だと主張しようと思ったことに対しても反例が集まってくるということで、普遍性といってもしょせんは傾向でしか捉えられないという議論になってきて、このtypologyという分野も、残念ながら最近は多少輝きを失って来ているのではないかと思います。
ではいま、何を励みにしているのかということですが、個別言語の記述、特にフィールド言語学をやっている人間としては非常に困った状況に陥ったわけですが、ある意味ではそれに救いの手を差しのべたのが、変な話ですが、国連であります。
国連は2年前だったのでしょうか、「原住民年」を制定いたしました。これに呼応する形で、現在さまざまな言語が失われているという状況(言語の消滅というのはずうっと昔からあったわけでして、なにも今に始まった訳ではないのですが)を強調しまして、このような言語、endangered languagesを記述しなければいけないという、今度は理論的な観点からではなくて、非常にポリティカルな観点から、またフィールド言語学に対する目的意識を取り戻そうということを行っているのではないのかと思います。
ただしょせんはやはりこれも外部からの正当化でして、やはりフィールド言語学者がずうっと持ち続けてきていた、個別言語の記述研究というものの内部で、ある理論化、体系化というものができないかという要望、欲求を満たすものではなかったわけです。では今後どのようにすればいいのか。われわれはやはりしょせん言語学の中の肉体労働者として、データコレクションに専念するという形で進まざるを得ないのか。つまりフィールド言語学の外にある体系、ある理論というものに奉仕する形で、長沢さんがおっしゃった、まさにある意味では安楽な環境の中に安住して、これから過ごして行くべきなのでしょうか。私は、ちょっと無理遣りではありますけれども、フィールド言語学、あるいは広くフィールドワークが提起できる一つの新しい分野というものがあるのではないのかと思います。
それは、やはり皆さんのいままでのお話の中にあったことだとは思うのですが、現実、あるいは事実というものがあるとしまして、それをわれわれがどのように記述していくのか、物事をどのように理解していくのか。先ほど加藤さんは天文学のアナロジーをお使いになってお話ししました。ただ人文学の場合に天文学と違うのは、天文学のような自然科学の場合は、データ収集に関する理論、例えば実験計画法ですとか、そうした体系が確立しています。
ところがそれに比べまして、人文学は、特にフィールドワークというものは、センサーとしては人間個人の体験、あるいは経験しかないということです。われわれの目で見て、耳で聞くと思っていますが、やはりそれは経験としてそこにある結晶化をしない限り、やはりデータとはなり得ない。最近特に人類学の若手の方々からは、むしろ記述、あるいは観察をかなり積極的に見直すという議論が起こっています。つまりデータをどのように自分の中に取り込んで行くのか、あるいはデータ化しているのかというそのプロセスの反省、そして調査者、あるいは観察者自体をも記述の範囲に取り込むような枠組みを構築するという必要がありはしないかということを、かなり無理遣りですが、ひとつ、フィールドワークの分野としては提案できるのではないのかと思います。
それから同じような意味で、そのデータをアウトプットする場合の問題というのがあります。われわれはデータを客観的な事実として、ある客体化されたものとしてついイメージしがちですが、やはりデータの提示にはいろいろな落とし穴があります。以前A研の小さな研究会で、人文科学データの提示法、プレゼンテーションというようなことをやりました。そこでいろいろな分野の方に話していただきましたが、統計学から社会科学まで、いろいろデータの提示ということに問題を抱えていらっしゃる研究者の方の話を伺いまして、大変参考になりました。といったわけで、あくまでフィールドワークとしてはデータにこだわり、もちろんデータはある種の人工的なコンストラクトなわけですが、その扱いということ自体を、あるいは調査という営み自体を問題にするというような可能性があるのかもしれないと思います。私は今度の佐藤さんを代表者とするプロジェクトの一員ではないので、ある意味では非常に無責任にいえるわけですが、このプロジェクトでも、ちょっとご検討いただけないかということで、提案させていただくわけです。
もう一つは、そのような多少抽象的な議論とは別に、われわれはもうそろそろかなり研究手法に関する具体的な議論をするべき時に来ているのではないのかという気がいたします。地域研究というのは、ある意味では通常いわれています学際的な研究というのに非常に適した分野ではないのかと思います。ただ、学際的な研究、あるいは共同研究といったものが、単に研究者が集まればできると、われわれは思い込んでいないのかなと私自身自問自答しています。
研究の延長線上に、あるいは個人研究の延長線上に共同研究があると思っている節がある。これまでそれで非常にうまくいってきた、たまたまうまくいってきたのだろうと思います。しかしある直轄研で研究している研究者の人から話を聞いたのですが、研究と共同研究と別なことではないのかとおっしゃっていました。つまり共同研究を行うのは、もちろんそれが研究であるのは確かなのですが、共同研究というものをオーガナイズしていくには、まったく別の才能、あるいは才覚というものが必要だろうと言うのです。それはむしろ企業運営などに非常に近いものになってくるのだろうということです。ですから、われわれが暗黙のうちに個人の研究を積み重ねて、その延長線上に共同研究を考えるとしたならば、やはりなかなか具体的な成果の上がらないという状況を繰り返していかなければならないのではないのかという、これは危惧であります。
ではこれまでなぜそのような共同研究がうまくいってきたのかということですが、それは、たまたまいままで中東地域研究を引っ張ってきたリーダーの方たちが、非常にエンタープライズの才能を同時に兼ね備えた方々だったから、そのような問題点が浮き上がらなかったのではないのかと思います。
ごちゃごちゃ申し上げましたが、私としては一つそのデータというものに関する問い直し、それからもう一つは非常にあまりにも日常的というか、現実的な話になってしまいますが、共同研究のオーガナイズの見直しという点を、もし可能でしたらこのプロジェクトの中でご検討いただければという希望を述べさせていただくことでコメントにしたいと思います。
オリエント学会フォーラム「過去から未来のイスラーム地域」
「地域研究という第三の道:歴史学の側から」レジュメ
How could be Area Studies the third alternative beyond the borders of Humanities and Social Sciences?
1997.10.25 三浦 徹(お茶の水女子大学)
Toru MIURA, Ochanomizu University
1)中東地域研究
・H.A.R. Gibb, "Area Study Reconsidered", 1963
東洋学と社会科学との結婚
古典的東洋学批判:
大文化=普遍的規範を研究←→地方社会=小文化の軽視
輻輳性complexityの軽視←→編年誌
伝統的東洋学者の文化理解への疑問を提示
文化の体質と伝統とを静態の存在とはみなさない把握力の必要(対象の広がり、関係性、なぜの重視)
・人文学:地域や人間の個別性、内在的世界理解←→社会科学:抽象的個人と普遍的社会モデル、因果関係
Said, Orientalism 社会科学の肯定的評価(ロダンソン、アブデレマレク、オーウェン)普遍的人間
社会科学 西欧近代の世界観
なぜイスラム史は世界史の蚊帳の外か(独自性と普遍性)
他分野との方法の交流の欠如、イスラームという要素の位置づけ
中東史(オリエント史)か、イスラム史か、近代史か
2)方法の比較
・人文学・社会科学・東洋学(オリエンタリズム)・文化史・社会史・世界システム論・日本のイスラム研究
要素 A世界的・B地域的、C物質的・D文化的、E構造・F個人
G資料、F階層性→図1、2、3、6
イスラームのねじれた位置 世界大、文化的、構造的
接近する領域 文化・シンボル 民衆文化、非文字文化、行動パターン、規範
非イスラーム的要素
3)比較の必要 →図4、5、6
・M.Bloch
A射程の長い比較(相互に影響関係のない時代・社会の比較)
B隣接する地域・時代の比較(影響関係の存在)
素朴実証主義、国民史への批判:編年誌による因果関係の立証
比較の必要:仮説設定とその検証、異なる諸社会の独自性の発見、新事実の発見
比較の単位:仮説に応じて自由に、時空を設定
・Th. Skocpol & M. Somers
a.Parallel demonstration of theory 一般理論の適用(一般理論適用型)
b.Contrast-oriented contexts 歴史を理解すべく概念を利用する(解釈学型)Geertz
c.Macro-causal analysis 歴史における因果規則性を分析する(分析型)Bloch
4)中世イスラム国家論の構造 →図7
モザイク社会 君主、軍人(マムルーク、遊牧軍人、alien)、名士(ウラマー)、コミュニティ(街区、fraternities、ethnic group, minorities)
公正な統治者 イスラームの倫理の実践、農民の保護、国家と社会/支配と被支配の分離、協力者としての軍人とウラマー
イスラームという共通の規範、そのもとでの異なる役割
変化 要素間の一致(協和)と分裂 君主と臣民の利害の一致(サラディン、バイバルス、マクリージー)
5)見直しの方向
・比較の方法 →図4
「イスラームではこうなっている」という論法を排し、比較を通して、普遍性と特殊性を説明する(オリエンタリズム、イスラム中心主義を排す)
比較の手法による因果関係の検証(イスラーム的ファクターの意識的な置き換え)
・個人と社会の接点としての行動パターン・規範、方法的個人主義
・様々な見直し
マムルークとウラマーの共通の文化 ヒエラルヒー、職と権益をめぐる競争、行政権益、家門
ヤクザ 任侠集団→暴力集団(清水和裕)
部族→行政、ワクフへの進出(近藤信彰)
スーフィー 聖者を核とした社会統合(私市正年)
賄賂と行政
オスマン国家 行政権集合体
システムとしてのイスラーム
イスラーム法 個人主義的、現実的(形式的)、地方的(柳橋博之)
市場社会(加藤博)、 ワクフ 市場的経済として(用益権)、経営体
モラル 個人宗教、天国と地獄、統治者像
バーゲニング 個人が状況に応じて取引 システムも価値観もカードにすぎない
→状況・コンテクストの理解、movementsを扱う個別研究の重要性
6)日本の中東・イスラーム研究
研究には国籍がある/欧米の研究の延長や精緻化でなく/オリジナリティ
[参考文献]
1.Burke, Edmund III, "The Sociology of Islam: The French Tradition", Malcolm H. Kerr ed., Islamic Studies: A Traditon and its Problems, LA, 1980.
2.id. Islamic History as World History: Marshall Hodgson, "The Venture of Islam", IJMES, 10, 1979
3.id. "Islam and Social Movements: Methodological Reflections", Edmund Burke, III, & Ira M. Lapidus, eds., Islam, Politics, and Social Movements, Berkeley & LA, 1988.
4.Lapidus, Ira M., "Islam and the Historical Experience of Muslim Peoples", Malcolm H. Kerr ed., Islamic Studies: A Traditon and its Problems, LA, 1980.
5.Hourani, Albert, "Islamic History, Middle Eastern History, Modern History", Malcolm H. Kerr ed., Islamic Studies: A Traditon and its Problems, LA, 1980.
6.Humphreys, R.Stephen, Islamic History: A Framework for Inquiry, Rev. ed, Princeton, 1991.
7.Owen, Roger, "Studying Islamic History", Journal of Interdisciplinary History, 4/2, 1973.
8.Skocpol, Theda & Margaret Somers, "The Uses of Comparative History in Macrosocial Inquiry", Comparative Studies in Society and History, 22/2, 1980
9.スコチポル、T.編著『歴史社会学の構想と戦略』木鐸社、1995。
10.ブロック、M.(高橋清徳訳)『比較史の方法』創文社、1978。
11.三浦徹・黒木英充・東長靖編『イスラーム研究ハンドブック』栄光教育文化研究所、1995。
12.三浦 徹「イスラーム地域研究の発進」『歴史学研究』702、1997。
13.三浦 徹(書評)「M・チェンバレン著『中世のダマスクス(1190-1350)における知と社会的実践』」『東洋学報』79/1、1997。
14.佐藤次高『イスラーム世界の興隆』中央公論社、1997。
15.Garcin, Jean-Claude, et. al., Etats, societes et cultures du monde musulman medieval Xe-XVe siecle, tome 1, Paris, 1995.
16.Haarmann, Ulrich ed., Geschichte der Arabischen Welt, Munchen, 1994.